その日は、風の音も心地よく、川沿いのサイクリングロードには人影もまばらだった。
K氏(仮名)は、週末になると自転車で10kmほど走る習慣があった。医療系の仕事をしており、平日の疲れを癒す時間でもある。
舗装路の端に何か違和感を覚えながらも、道なりに進む。前方に少し草が生い茂っていたため、路肩との境目が見づらい。

「…ガクッ!」
前輪が落ちた。
ほんの一瞬、空中で身体が浮いたのを感じる。
左側から地面に叩きつけられた衝撃。
その瞬間、強烈な痛みが左太腿を貫いた。
通行人の通報により救急搬送。診断は「左大腿骨骨折」、歩行回復には半年以上のリハビリを要するという。
入院中、K氏は思い返していた。
「なぜこんな事故が起きたのか?」
転倒の瞬間の映像は頭から離れない。
事故現場は、舗装路と土留めの間に約5センチの隙間があり、ちょうどタイヤが落ち込む幅だった。
しかも、その部分に警告表示はなかった。
知人に相談したところ、「それって行政の管理ミスじゃないか?」と言われる。
自治体の道路管理課に問い合わせるも、「特に瑕疵とは認めておらず、問題はないと考えています」という冷たい対応だった。
「誰も責任を取らないのか?」
その疑問が、K氏を法的手続きへと導いた。
地元の弁護士事務所を訪れたK氏。
弁護士は図面と現地写真を見ながら首をひねる。
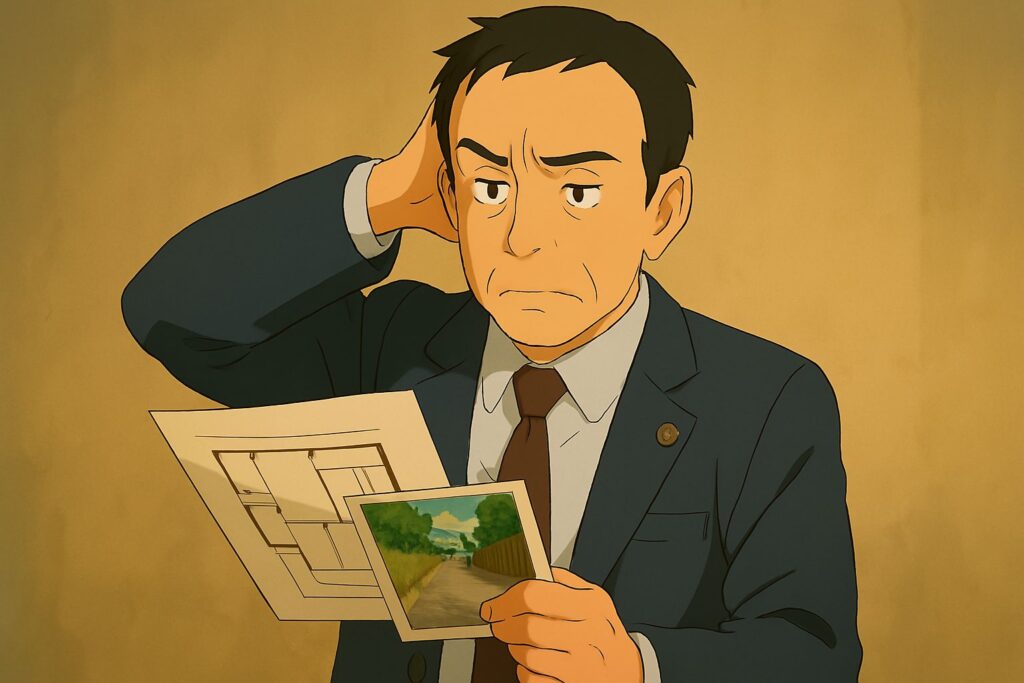
「これは…造形的には危険ですね。国家賠償法の可能性があります」
訴訟の提起には行政への損害賠償請求が必要となる。
弁護士は、実際に判例タイムズに似た事例が掲載されていることを紹介し、K氏は希望と不安を抱えながら訴訟に踏み切ることを決意した。
数週間後、地方裁判所に訴状が提出された。

請求内容は、転倒事故に関して自治体に責任があるとして約500万円の損害賠償。
自治体は書面で反論。
・舗装の設計は適切だった
・事故は本人の不注意によるもの
・隙間は「通常の利用において危険とまでは言えない」
弁護士は現地写真と実測データ、道路設計基準の解説をもとに「明らかに不自然な構造」であることを主張する。
証拠書類の準備は、専門家への依頼や工学的解析など膨大な労力を要した
👇自転車事故の関連記事
『小学2年生に60%の過失!?自転車事故判例から読み解く法の温度』
判例(東京高裁令和6年1月24日判決)

隙間は瑕疵と認定。
自治体に賠償責任あり。ただし原告にも1割の過失相殺。
🎙️こぱおの法律研究室
-1024x683.jpg)
-1-150x150.jpg)
いや〜、転倒事故の原因が「たった5センチの隙間」って、行政の責任もだいぶ細かいとこまで問われるようになったな~。
-150x150.jpg)
でも、その隙間で人生が大きく変わってしまうこともあるもふ。
怪我で半年リハビリって…日常のリスクって意外と深いもふぅ~。
-1-150x150.jpg)
国家賠償法の「瑕疵」って、けっこう曖昧なとこあるやん?今回は「舗装構造が通常の安全性を欠いてた」ってことで、裁判所がしっかり認定したわけだけど。
-150x150.jpg)
もふ~。利用者の過失が1割認められたのも興味深いもふ。
リスクはゼロにできないから、お互いが少しずつ責任を持つってこともふ。
-1-150x150.jpg)
それにしても、行政の「気づかれにくい瑕疵」って、言われなきゃずっと放置されてることもあるんじゃない?この判決、他の自治体にも刺さるんじゃないかな。
-150x150.jpg)
そう思うもふ。この判例は、都市の「リスクデザイン」に関わる哲学的な問いも含んでる気がするもふぅ。安全って、数値じゃなくて“気づかれない優しさ”で守るものかもしれないもふ。
-1-150x150.jpg)
……詩人か。まあでも、今回の判決って「公の施設にも想像力を」って言ってるようなもんだな。
-150x150.jpg)
もふ~。人が通る可能性がある場所には、“生活者の視点”を忘れずにいたいもふよ~。
こぱお博士の法的アドバイス
🧱 アドバイス①
「公の施設でも“見えない瑕疵”は存在する」
→ 国家賠償法2条1項は、行政の施設に“通常有すべき安全性”が欠けていれば、損害賠償責任が生じる。
こぱお:「舗装の隙間は、法の隙間でもある。見逃すと骨が折れるぞぃ」
🧍♂️ アドバイス②
「利用者にも注意義務はある。だが、限界もある」
→ 判例では原告にも1割の過失相殺。
こぱお:「目を凝らしても見えない隙間に落ちたら、それは“注意義務の限界”や。人間の目は顕微鏡ちゃうぞぃ」
🏛️ アドバイス③
「行政は“安全”を設計する責任者である」
→ 設計段階でのリスク評価と点検体制が問われる。
こぱお:「予算が足りん? なら“安全設計費”をクラウドファンディングで集めるがよい。ワイが1円だけ出すぞぃ」
📸 アドバイス④
「事故現場の記録は、法廷での“証拠の命”」
→ 写真・動画・図面・現地調査が判決を左右する。
こぱお:「スマホのカメラは、現代の“法の目”や。転んだらまず撮れ。痛みより先に証拠やぞぃ」
🧃 アドバイス⑤
「判例は“過去の答え”であって、“未来の正解”ではない」
→ 判例は参考にすべきだが、事案ごとに吟味が必要。
こぱお:「ワイは判例タイムズを枕にして寝とるが、夢の中では毎回違う判決が出とる。つまり、法は生き物や」
👇「この一杯が、次の判例解説を生むかもしれんぞぃ」☕️
コーヒー代 300円もふん補佐官の見解🐾
🕊️ 1. 公共空間の責任について
「サイクリングロードは、誰かの休日の風景です。
でも、その風景の中に“誰も気づかない危険”があったなら……それは、誰の責任でしょうか……もふん」
→ もふんは、行政の設計と管理に“生活者の視点”が欠けていたことを静かに指摘します。
🧠 2. 法の言葉と人の痛み
「国家賠償法には、“瑕疵”という言葉があります。
でも、判決文に書かれない“痛み”や“悔しさ”も、そこに含まれていると思うのです……もふん」
→ 法律は冷静でも、もふんはその裏にある感情や人生の変化を見逃しません。
🧍♂️ 3. 利用者の注意義務について
「注意していても、見えないものはあります。
それを“過失”と呼ぶなら……人はどこまで慎重になればいいのでしょうか……もふん」
→ もふんは、過失相殺の判断に対しても、静かに問いかけます。人間の限界を理解した上での優しさです。
🌱 4. 社会への問いかけ
「この判例は、“安全”という言葉の意味を、もう一度考えさせてくれます。
それは、誰かが転ばないようにすることだけじゃなくて……転んだ人に、ちゃんと向き合うことでもあると思うのです……もふん」🐾
→ もふんの見解は、判例を通じて社会のあり方そのものに静かに問いを投げかけます。
👇「ドーナツは、心の判例をやさしく包む円……もふん」🍩
ドーナツ代 500円OFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます
『小学2年生に60%の過失!?自転車事故判例から読み解く法の温度』
このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。
気になる方は、ぜひぜひブックマークしておいてください!
この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!
X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw






-120x90.jpg)
コメント