地下二階、ザワつく会議室
📍場所:行列のできるなんでも法律研究所・地下二階「会議室」
📅 時刻:2025年7月21日・参院選直後
-1024x683.jpg)
(書類抱えて慌てて登場)
博士ぁ〜〜!
大変です!参政党が14議席もふ!
(眉一つ動かさずに眼鏡をくいっ)
ほう…ついに“法案提出権”の壁を超えたか。
ほむ、これは…まさに制度のフロンティアが動いた瞬間だな
👇参政党の解説記事はこちら
法案提出権の“壁”を超えた衝撃──参政党は制度上、何を手にしたのか?

2025年7月の参院選で、参政党が14議席を獲得。
この数字は、単なる“勢い”ではない。
法律家の目線で見れば、制度の分岐点とも呼べる出来事である。
国会法第56条では、参院の場合「10人以上の議員の賛同があれば法案を提出できる」。
つまり、11議席以上あれば政党単独でも法案提出権を持てる。
参政党はこの基準を超え、「法的プレイヤー」としての地位を確立した。
これは、少数政党が立法手段を持たない“提案止まり”状態から、制度設計そのものに関与する可能性が生まれたことを意味する。
政策が通るかどうかではなく、法案を出すことで他党と交渉する権利が生まれる――それが「提出権」という武器である。
たとえば過去、社民党やみんなの党などもこのラインを境に影響力を大きく伸ばした。
法案提出権の獲得は、政党が「理念を掲げる集団」から「制度と交渉に挑む集団」へと進化する通過儀礼なのだ。
“日本人ファースト”政策の吸引力と法的課題
参政党が掲げる「日本人ファースト」というスローガンは、多くの有権者にインパクトを与えた。
移民政策への不安、国籍への帰属意識、生活保障の公平性――そうした“感情の波”に乗って、参政党は比例代表でも第2党に浮上する得票率を記録した。
しかし、法的視点から見れば、この政策群は憲法との緊張関係を抱えている。
血統による公務制限──憲法14条「法の下の平等」との衝突
参政党が公開している「新憲法草案」には、「帰化人の孫まで公務員になれない」とする条文が盛り込まれている。
これは、出身や血統によって公的職務への参加が制限されるものであり、現行憲法14条が保障する平等原則に明確に反する。
「すべて国民は、法の下に平等であって…人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」
この条文は、「本人の意思や行動ではなく、血筋によって扱いを変える」ことを禁じるもの。
参政党の草案は、「個人ではなく血統」を判断基準にしており、差別概念の中でも構造的・制度的な排除とされる危険性が高い。
外国人への生活保護停止──憲法25条「生存権」と最高裁判例
さらに、参政党の政策には「外国人の生活保護を停止する」と明記されている。
これも、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」との関係で議論を呼ぶ。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
ここでの問題は、“外国人は憲法で守られない”という単純な話ではない。
2002年の最高裁判例では、「永住資格を持つ外国人も生活保護制度の枠組みに含まれる」と判断されており、完全な排除は違憲性を帯びる可能性がある。
憲法は「国民の権利」だけでなく、「国家の運用原理」にも適用される。
参政党の主張は、支持者の感情には響くが、制度運営上は人権・福祉・憲法秩序とのせめぎ合いになるのだ。
まとめ:法と感情の間に立つ政策群
参政党の政策は、国民の感覚に寄り添うものが多い。しかし、憲法は“感覚”ではなく“原理”で構成されている。
「日本人ファースト」が求める帰属意識と、「憲法が保障する普遍的な人権」との間には、理性的な調整と制度的な熟慮が必要になる。
この章では、「スローガン」と「制度設計」の距離を見つめながら、参政党がいかなる立法の方向へ進むのかを探る土台となった。
積極財政と“150兆円国債”──理想と現実の落としどころ
参政党は、消費税ゼロ・子育て支援(月10万円)・教育国債・デジタル通貨など、国民生活を底上げする大胆な政策を掲げている。
その財源として提示されたのが、「150兆円の国債発行」という規模感だ。

だが、これはただの数字ではない。日本のGDPの約3割に相当する巨額であり、金融・財政・市場の構造を大きく揺さぶる可能性がある。
金利上昇と民間の圧迫
国債が大量発行されれば、国の借金が増える。市場はその信用リスクに応じて金利を上昇させる。
これは、民間企業や家庭が借りるコストにも波及し、経済全体の投資意欲を下げる要因になる。
また、金利上昇は財政にも跳ね返る。将来の利払い額が膨らめば、**福祉や教育などの予算を圧迫する“逆再配分”**が起きかねない。
現代貨幣理論(MMT)との親和性と限界
参政党の主張は、現代貨幣理論(MMT)と一部重なる。
MMTでは「政府は自国通貨を発行できるため、財源不足にはならない」という前提がある。
確かに、通貨発行権を持つ政府は“破産”しない。
だがこれはあくまでインフレ管理や市場との信頼が維持されることが前提条件。
信頼を失えば通貨は暴落し、社会は急激な価格変動に晒される。
つまり、国債=魔法ではなく、信用という繊細な資産に支えられた制度なのだ。
政策提案としての意味──理想の提示と現実の交渉力
参政党の財政方針は、国民の不満や不安に具体的な“希望”を提示した点で意義深い。
特に子育て支援や地方教育への投資は、社会的ニーズの高い分野である。
ただし、現実に制度として実現するには、既存の財政規律や金融政策との橋渡しが不可欠。
橋下徹氏との討論でも浮かび上がったように、理想と実装の間には**“数式ではなく政治”という壁**が存在する。
まとめ:積極財政は希望か暴走か
国債150兆円という数字は、参政党の「未来構想」の象徴だ。
しかしその実現には、財源設計・市場理解・制度調整という3つの法的リテラシーが求められる。
大胆な理想は必要だが、それを社会に繋ぐ“現実の橋”を設計する力こそが立法の本質である。
右派でも左派でもない──“第三極”としての参政党
参政党の政策は、一見すると保守的で右派寄りに見える。
たとえば移民制限・外国人生活保護の停止・土地購入の制限といった「日本人優先」を掲げる内容は、国家主義的な論調と親和性が高い。
しかし一方で、積極財政・消費税ゼロ・教育国債・地方支援など、財政出動型の経済政策は、従来の左派的視点に近い。
この“左右混成”のスタンスが、参政党をイデオロギーの地図の外側に押し上げている。
なぜ“第三極”と呼ばれるのか?
日本の政党スペクトラムは、概ね以下のような分類がなされてきた
| 区分 | 主な政党 | 特徴 |
|---|---|---|
| 保守(右) | 自民・維新 | 秩序・市場原理・国防重視 |
| リベラル(左) | 立憲・れいわ | 人権・福祉・再分配重視 |
| 中道・ポピュリズム | 国民民主・参政党 | 生活重視・混合型政策・現状批判 |
参政党は、移民・国籍などでは保守的主張を取りつつ、経済や教育では国民生活支援型政策を展開。
この“混在性”こそが、既存政党の枠組みでは位置づけづらい第三極的性格と言える。
ポジショニングの課題と可能性
第三極政党には、“既存政党批判”による支持を集める反面、「具体的な制度構築力」が問われる。
参政党も、憲法や財政などに対する批判や新構想は提示できるが、それが現行制度とどう接続されるかが今後の焦点になる。
また、票の奪い合いは必至だ。国民民主党やれいわ新選組と政策的に重なる部分も多く、競合状態に入りつつある。
それでも、参政党が掲げる「統合された日本人意識」「自然志向の生活設計」「草の根民主主義」は、特定の支持層に深く刺さる世界観を持っている。
まとめ:イデオロギーの地図を再構築する存在
参政党は、右でも左でもない。
むしろ、「価値観と生活設計を結びつける政党」として、これまでの政治の地図に新たな軸を加える存在になっている。
“第三極”とは、単なる中間ではなく新たな世界観への挑戦。それが今、国政の制度設計に影響を与える段階へと踏み出した。
制度に残す痕跡──立法プレイヤーとしての参政党
参政党は、14議席獲得によって国会の“観客席”から“プレイヤーズ・ベンチ”へと席を移した。
法案提出権を持つ政党として、今後は単なる意見表明ではなく法制度に形を残す役割を果たしていく。
実際に制度は変わるのか?
法案提出権は立法の起点である。提出された法案が通らなくても、それは議論の方向性を定義する役割を持つ。
参政党が提出する法案は、他党の対応によって部分的に吸収されたり、代案として形を変えて通ることもある。
つまり、「提出=変化の予告」であり、「通過=制度の痕跡」になるのだ。
これは、参政党が制度形成に足跡を残す段階に入ったことを示している。
他党との連携か、単独路線か?
この先、参政党が選ぶ道は2つ。
- 連携型プレイヤー:国民民主党や維新の会などと政策テーマごとに共闘し、制度改革を共有する道
- 単独型プレイヤー:独自法案を提出し続けることで、“自党の世界観”を定着させる道
どちらにせよ、法案提出権のある政党は制度設計者としての資格を持つ。
その資格を使って何を描くかが、次のステージでの実力差となる。
社会に問いかける“制度の物語”
参政党の登場は、制度の硬直化に一石を投じた。
人権と国籍、財政と福祉、憲法と暮らし──それらを「物語」にして法案という形で提示することが、立法プレイヤーの使命だ。
社会に「これは制度として語るに値するか?」と問い続ける、その姿勢こそが、**制度に残る“物語の痕跡”**となる。
結論:「制度は語られる者に委ねられる」
参政党の“制度プレイヤー化”は、今後の国会をより多様な解釈と価値観で満たす契機になるだろう。
法案提出権とは、単なる記録ではなく、**制度と社会をつなぐ“問いの形”**なのだ。
👇法律を学びたい方はこちら(会員登録無料)
「制度に残る問い、そして次なる事件へ──地下二階にて」
📍場所:行列のできるなんでも法律研究所・地下二階のこぱおの法律研究室。
夜更け、ほこりの舞う資料棚に月光が差し込む。
-1024x683.jpg)
(紅茶を手に静かに)
-150x150.jpg)
博士、今回の調査…すごいボリュームもふ。
制度って、こんなにも“想い”と“構造”が絡み合ってるもふね…
(ゆっくり眼鏡を外して)
-1-150x150.jpg)
ほむ。
政策は“叫び”だが、制度は“問い”だからな。
参政党が掲げた14の議席の向こうに、国民の選択と葛藤が見えた…
(資料棚を見上げながら)
-150x150.jpg)
でも、博士はいつも迷わず向き合うもふ。
法って、そんなに強いものなんですか?
(資料にそっと手を置きながら)
-150x150.jpg)
法は強くない。
だが、それに向き合う者の問いが強い。
そして…ふん、次回の依頼が来ている。
『地方自治体がAI市長を導入したが、憲法上問題があるらしい』。
この研究所の地下は、いつだって事件だらけだ
(目を輝かせて)
-150x150.jpg)
ま、また濃いやつ来ましたね…!やりましょう、博士!
(ニヤリと)
-150x150.jpg)
地下二階に静寂はない。
法と物語がある限り、我々の出番は終わらんよ
🕯️(暗転…次回へ続く)
👇「よかったら、応援ボタンをポチッと…!」
OFUSEで応援を送る関連記事👇

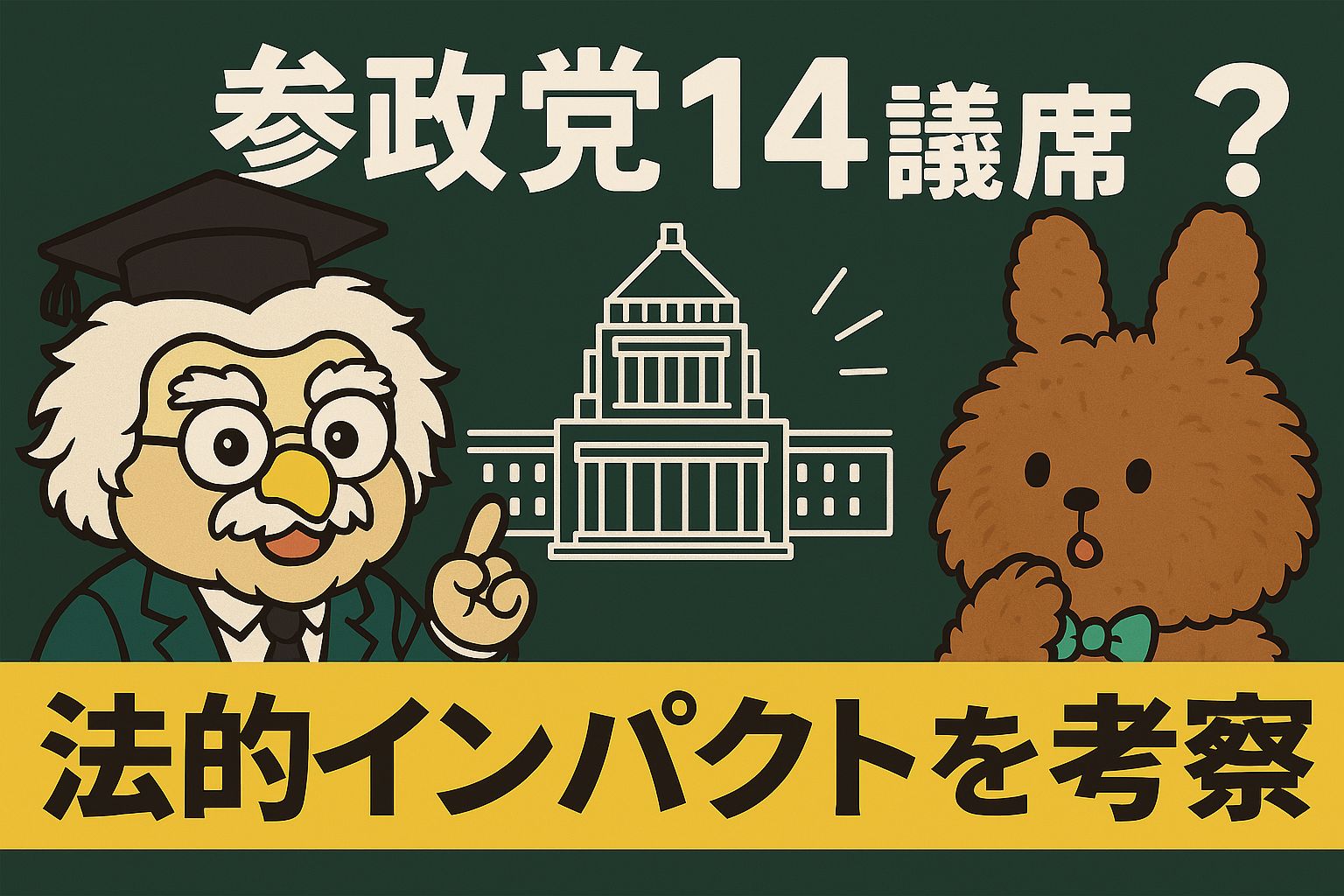





コメント