板橋団地、夕暮れの階段室
団地の階段室には、夕方になると子どもたちの声が響く。
東京・板橋区のこの団地に、**三浦恵(みうら・めぐみ)**はひとりで暮らしていた。
築50年の3DK。
かつては夫と娘と3人で暮らしていたが、今は彼女だけが残っている。

恵は、元保育士。
定年後、パートで働いていたが、夫の病気と葬儀費用で生活が傾き、カードローンに手を出した。
気づけば借金は400万円を超え、年金だけでは返済できない。
娘には言えなかった。
「この家だけは、残したいの。ここで、あの子を育てたから」
彼女は個人再生を決意した。
借金を減額し、住宅ローンはそのまま返済して団地を守る――それが「住宅ローン特則」のはずだった。
だが、問題があった。
団地の名義は、亡き夫のままだった。
恵は相続登記をしていなかった。
さらに、団地には夫の事業資金の抵当権が残っていた。
「名義が違うと、住宅ローン特則は使えません。抵当権も、住宅ローン以外のものがあるとダメなんです」

司法書士の言葉に、恵は黙った。
この家は、彼女の人生そのものだった。
娘の成長、夫との別れ、そして今の孤独。
だが、法は「名義」と「抵当権」で判断する。
その夜、恵は団地の階段室に座り、娘が小学生だった頃の写真を見つめた。
ランドセルを背負って、夕焼けの中を駆けていたあの姿。
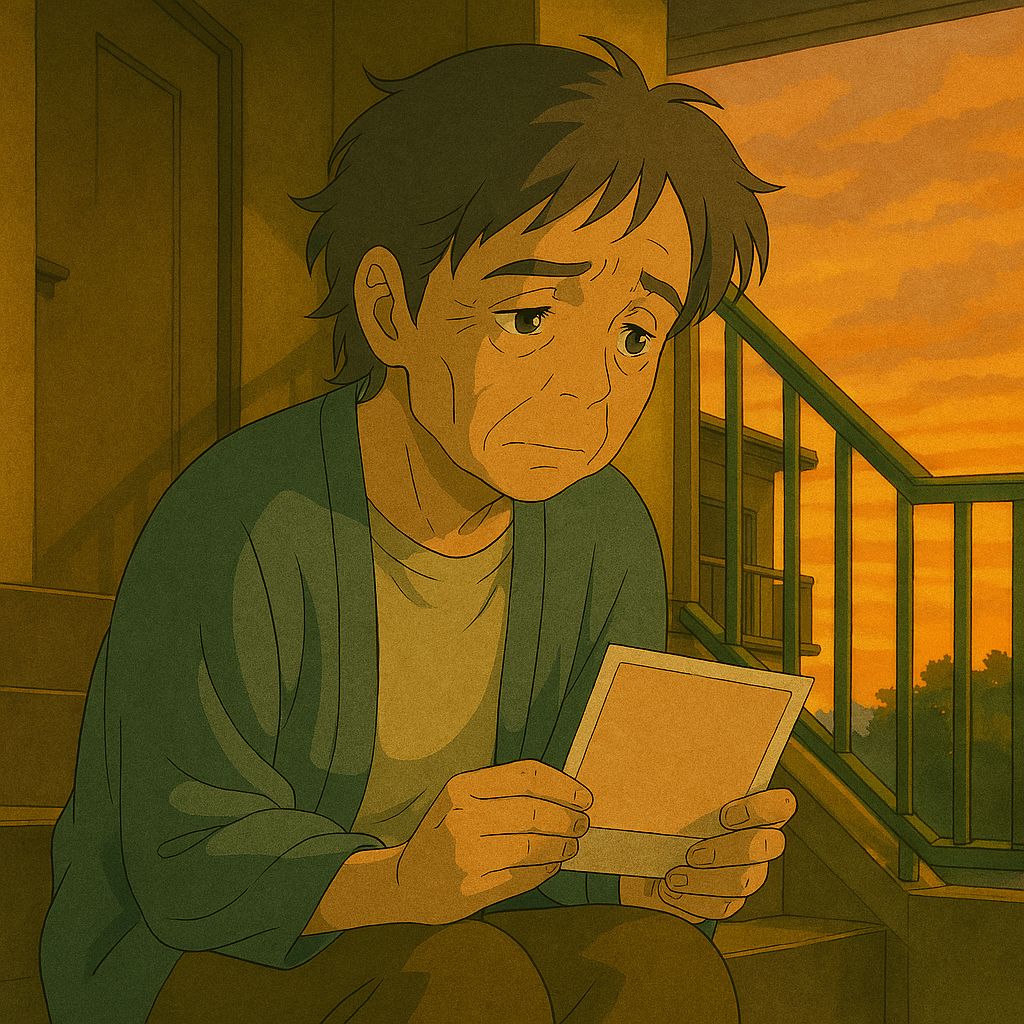
「この家は、私の記憶の箱なのよ」
👇債務整理はこちら(メール相談無料)
住宅ローン特則ってなに?

一言でいうと…
借金を減らす手続き(個人再生)をしても、家だけは手放さずに済むようにする特別ルールです。
どういう状況で使うの?
たとえば――
- カードローンや消費者金融からの借金が増えて、返せなくなった。
- でも、住宅ローンを組んで買った家には住み続けたい。
- そんなときに「個人再生」という制度を使って、借金を減らすことができます。
でも普通は、住宅ローンも含めて全部の借金が対象になるので、家を手放すことになる可能性が高い。
そこで登場するのが「住宅ローン特則」。
この特則を使うとどうなる?
- 住宅ローンだけは減らさずに、今まで通り返済を続ける。
- 他の借金(カードローンなど)は大幅に減額される。
- つまり、家を守りながら借金整理ができる!
⚠️ ただし、使える人には条件がある
以下のような条件を満たしていないと使えません👇
・実際にその住宅に住んでいること
→ 空き家や賃貸中の物件では適用されません。
・住宅の床面積の50%以上が居住用であること
→ 店舗併用住宅やアトリエ併設住宅は要注意です。
・住宅ローンが家の購入・建築目的であること
→ 事業資金やリフォームローンなどは対象外です。
・住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
→ 他の借金の担保になっていると適用できません。
・住宅ローンの滞納がない、または代位弁済から6ヶ月以内であること
→ 滞納が長期化している場合は特則の利用が認められません。
まとめ
住宅ローン特則は、「家を守りたい人」のための制度。
でも、形式的な条件が厳しくて、実際には使えないケースもある。
だからこそ、制度の仕組みを知っておくことが大切です。
👇債務整理の他の記事はこちら
債務整理の受任通知後に弁済すると否認される?最高裁判例と事例で解説 | 行列のできるなんでも法律研究所
判例解説:住宅ローン特則の適用可否

この物語の背景には、実際の裁判例や制度運用がある。
争点
住宅ローン特則は、形式的要件を満たさないと適用されない。
実際に居住していても、名義が違ったり、他の抵当権があるとアウト。
判例(東京地裁令和元年)

- 債務者が住宅に居住していたが、名義が元配偶者のまま。
- 他の抵当権(事業資金)が設定されていた。
- 裁判所は「住宅ローン特則の適用不可」と判断。
法の論理
- 民事再生法196条は「債務者本人が所有する居住用建物」に限定。
- 他の抵当権があると、住宅ローンの返済継続が困難と判断される。
- 実態よりも「形式的な要件充足」が優先される。
法律研究室:こぱお博士ともふん補佐官の対話
-1024x683.jpg)
場所は、法律研究室。
こぱお博士は、民事再生法の逐条解説を読みながら、もふん補佐官に語りかける。
博士、三浦さんはずっとその団地に住んでたんですよ。
名義が違うだけで、家を守れないなんて…
法は“所有”を守る。
“記憶”や“生活”は、制度の外にある。
だが、それを拾い上げるのが物語の役割だ
じゃあ、法は“誰の家か”を登記で決める。
でも、“誰の人生か”は、誰が決めるんですか?
それは、読者だよ。
判例が切り捨てたものを、読者が拾い上げる。
それが、法と文学の交差点だ
こぱお博士の見解:制度の線引きと守られなかった家
民事再生法における住宅資金特別条項――いわゆる住宅ローン特則は、債務者の生活再建を支える制度として設計された。
だが、その適用には、あまりに厳密な形式的要件が課されている。
名義、抵当権、居住面積、滞納状況。
いずれか一つでも満たさなければ、制度は債務者の「家」を守らない。
私はこの制度に、ある種の“冷たさ”を感じる。
だが、それは単なる非情ではない。
法は、感情に流されないことで、均衡を保つ。
公平性を担保するために、形式に依拠する。
その冷たさは、制度の安定性の代償でもある。
しかし、問題はこうだ。
制度が守る「家」とは何か。
登記簿に記された所有権か。
床面積で測られた居住性か。
金融機関が納得する返済可能性か。
それらはすべて、法的構造物としての「家」にすぎない。
だが、債務者が守りたい「家」は、そうではない。
そこには記憶があり、生活があり、関係性がある。
団地の階段室で娘を見送った朝。
アトリエの窓辺で描いた絵。
夫と過ごした最後の冬。
それらは、法では測れない。
だが、確かに「家」の一部なのだ。
住宅ローン特則は、制度の中で「家」を守ろうとする。
だが、制度の外にある「家」は、守られない。
そして、その外側にこそ、人間の生活の本質がある。
私は思う。
判例が切り捨てたものを、物語が拾い上げるべきだと。
法が見落とした生活の温度を、文章が照らすべきだと。
制度の限界を描くことは、制度を否定することではない。
それは、制度の外にある人間の尊厳を、そっと差し出す行為なのだ。
🐾もふん補佐官の見解:守られなかった生活と、制度のまなざし
私は、三浦さんの団地を見た。
階段室の壁には、子どもの落書きが残っていて、郵便受けには娘さんからの手紙が挟まっていた。
そこには、確かに「生活」があった。
誰かが毎日、そこに帰ってきて、誰かを思いながら暮らしていた痕跡があった。
でも、法はそれを見ない。
法が見るのは、登記簿の名前。
抵当権の種類。
居住面積の割合。
それが制度の「まなざし」だ。
住宅ローン特則は、家を守る制度だという。
けれど、守られるのは「制度が定義した家」だけだ。
生活の実態があっても、名義が違えば守られない。
記憶が染みついていても、面積が足りなければ守られない。
それって、本当に「再生」なのか?
私は思う。
制度が線引きするのは仕方ない。
でも、その線の外にいる人たちを、誰が見ているのか。
誰が、彼らの「家」を守るのか。
三浦さんは、団地を失った。
でも、団地の階段室には、まだ彼女の暮らしの痕跡が残っている。
それを見つけるのは、制度じゃない。
私たちの目だ。
そして、それを語るのは、物語の力だ。
法が見落としたものを、拾い上げる。
それが、私たちの仕事だと思う。
🗣 読者の皆様への問いかけ
あなたの「家」は、誰のものですか?
登記簿にある名前か、記憶に刻まれた時間か――法が守るのは、どちらでしょう。
👇債務整理の他の記事はこちら

👇ご支援よろしくお願いします。
OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。
このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。
気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!
この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!
X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw
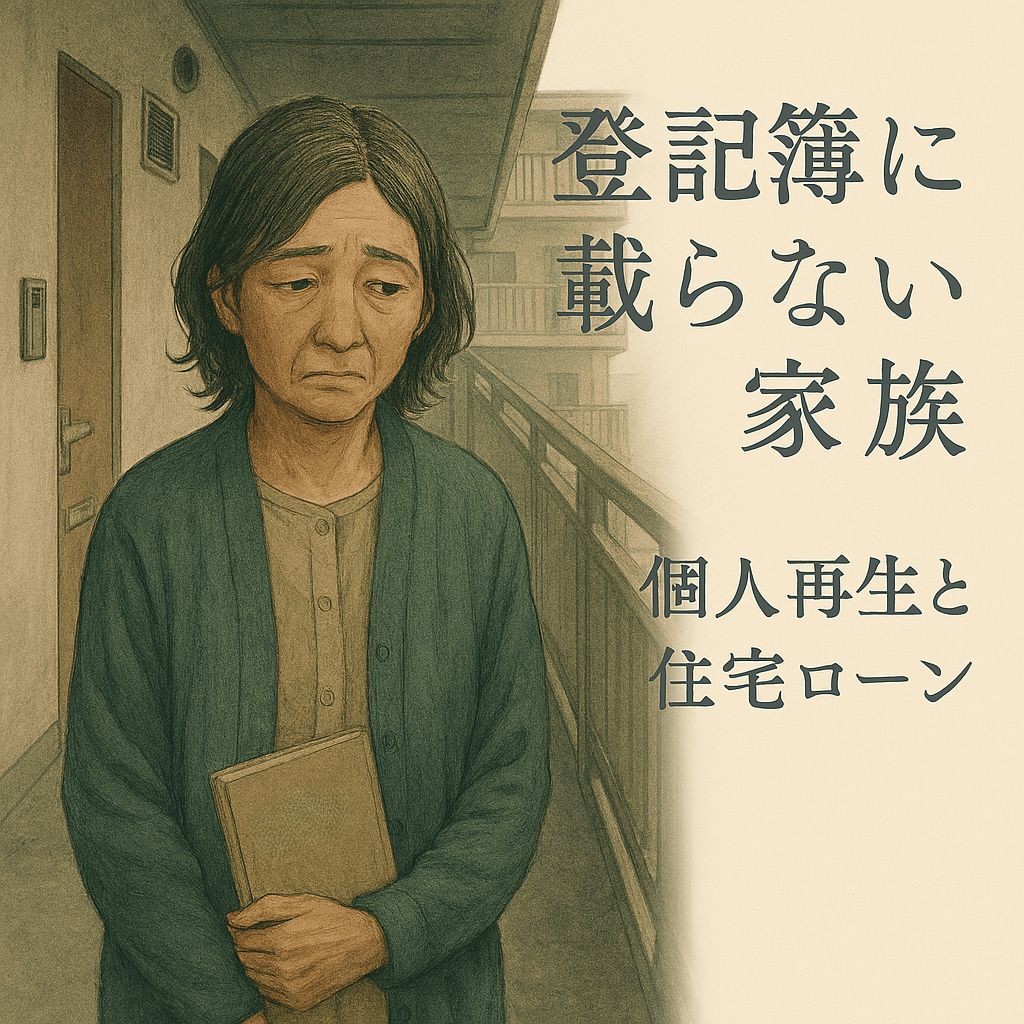
-150x150.jpg)
-1-150x150.jpg)







コメント