「沈黙の家計簿」
秋の終わり、雨がしとしとと降る午後。
陽介は、リビングのテーブルに書類を並べていた。

医師としての冷静さを保ちながらも、指先はわずかに震えていた。
向かいに座る麻衣は、白いニットに身を包み、湯気の立つ紅茶を見つめていた。

目は合わない。
言葉もない。

この10年で、君の収入は3,000万を超えてる。
なのに、別居時の預金は300万もない。
どういうことだ?
陽介の声は低く、しかし確かに怒りを含んでいた。
麻衣は紅茶に口をつけ、静かにカップを置いた。

生活費。
教育費。
親の介護。
全部、必要な支出だったわ

領収書は?
明細は?
証拠がなければ、財産分与の対象にならない。
隠してると思われても仕方ないだろ

隠してなんかない。
使ったのよ。
あなたが家計に関心を持たなかっただけ
沈黙――。
壁の時計が、秒針を刻む音だけが響く。

陽介は、机の端に置かれた古い家計簿を手に取った。
ページをめくると、数年前の記録が途切れていた。

この空白の期間、何があったんだ?
麻衣は目を伏せた。

記録する暇なんてなかった。
病院と家の往復で、毎日が戦場だった
陽介は立ち上がり、窓の外を見た。
雨は止みかけていたが、空はまだ重く曇っていた。

裁判所は、感情じゃなく証拠を見る。
君の“使った”は、僕の“隠した”に見えるかもしれない
その言葉に、麻衣は初めて陽介を見た。
目の奥に、疲れと悔しさと、わずかな哀しみがあった。

じゃあ、証明してみせる。私の10年を

👇財産分与の他の記事はこちら
退職金だけの分与は認められる?オーバーローン住宅と財産分与の境界線
👇無料査定はこちら
裁判所にて「証拠の壁」

登場人物
裁判官・田島(冷静沈着、証拠主義)
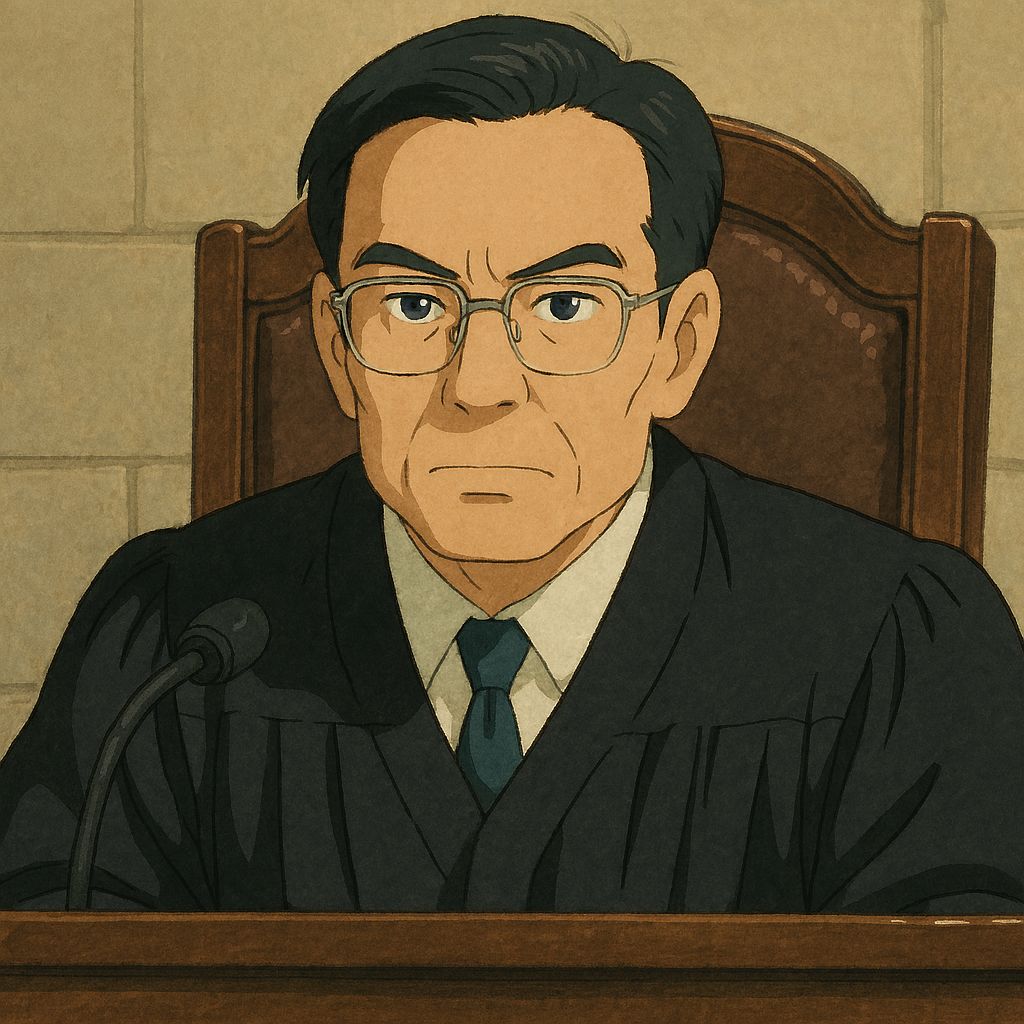
陽介(夫、几帳面で疑い深い)

麻衣(妻、合理的で感情を抑える)
.jpg)
(書類を見ながら)

本件は、財産分与における預金の存在が争点です。
妻の収入は高額である一方、別居時の残高が著しく少ない。
夫側は“隠匿”を主張しています
(前のめりに)

裁判官、彼女の年収は1,000万を超えていました。
10年で3,000万以上。なのに残高は300万。これは不自然です。
離婚を見越して資産を移したとしか思えません
(静かに)
-150x150.jpg)
生活費、教育費、親の介護。
支出はすべて必要なものでした。隠してなどいません

支出の証明はありますか?領収書、通帳、家計簿など
(少し間を置いて)
-150x150.jpg)
一部はありますが、すべてではありません。
記録する余裕がなかった時期もあります
(食い気味に)

それが“隠した”証拠です。
記録がないなら、貯蓄があったと推定されるべきです
(冷静に)

推定は証拠に基づいて行います。
支出の傾向、生活水準、教育費などを総合的に判断します
「あなたなら、10年分の支出を説明できますか?
記憶は曖昧。記録は不完全。
“使った”と“隠した”の境界線は、紙一重なのです」
👇財産分与の他の記事はこちら
「退職金は財産分与の対象?将来支給予定でも認められる判例を徹底解説」
財産分与判例のポイント解説(大阪高裁令和3年8月27日)

1. 財産分与の基本的な考え方
- 目的:婚姻中に築いた共同財産の清算+離婚後の生活保障
- 法的根拠:民法768条
- 清算的財産分与(最も基本)
- 扶養的財産分与(生活困窮者への支援)
- 慰謝料的財産分与(精神的苦痛への配慮)
2. 判例の具体的判断(大阪高裁令和3年8月27日)
🔍争点
- 妻が高額収入(年収1,000万円以上)を得ていたにもかかわらず、別居時の預金が300万円未満。
- 夫は「離婚に備えて資産を隠した」と主張し、10年分の口座履歴開示を求めた。
⚖️裁判所の判断(大阪高裁令和3年8月27日判決)
- 妻の支出に関する証拠は不十分だったが、生活費・教育費・親の介護などの支出状況を考慮。
- 「2〜3割程度の貯蓄は可能だった」と認定しつつも、隠し財産の存在は認めず。
- 結果:夫の主張は退けられ、財産分与の対象にはならなかった。
👇弁護士の探偵事務所はこちら(無料相談)
法律研究所・雑談室
-1024x683.jpg)
テーマ:財産分与と“隠し財産”の境界線
(雑談室。こぱお博士は分厚い判例集をめくりながら、もふん補佐官はクッションに埋もれて紅茶を飲んでいる)
(眼鏡を押し上げながら)
もふん君、君は“使った”と“隠した”の違いをどう定義するかね?
(紅茶をすすりながら)
えーと、使ったのは心の記憶に残ってるやつ。
隠したのは、相手に見せたくないやつ。
つまり、愛があるかどうかじゃないですか?
(眉をひそめて)
感情論だな。
判例では“証拠があるかどうか”がすべてだ。
大阪高裁令和3年判決でも、妻の支出に証拠がなかったから、夫は“隠した”と主張した
(クッションを抱えて)
でもさ、医師として働いて、親の介護して、子どもの教育費も出して…そんな生活の中で、全部記録するなんて無理じゃない?
(判例集を閉じて)
それは裁判所も考慮していた。
だから“2〜3割の貯蓄は可能だった”と認定しつつも、隠し財産の存在は否定した。
つまり、“合理的な支出”と見なしたわけだ
(ぽつりと)
証拠がないと、人生の努力も“疑い”に変わるんだね…
(静かに)
だからこそ、記録は“愛の証明”でもある。
家計簿は、未来への防衛線だ
(目を輝かせて)
じゃあ、家計簿に“ありがとう”って書いてもいいですか?
(微笑みながら)
それは証拠にはならんが、心には残るだろう
👇法律を学びたい方はこちら(会員登録無料)
こぱお博士の見解:「隠し財産とは“証拠の不在”が生む疑念である」
「隠し財産とは“証拠の不在”が生む疑念である」
「財産分与において、“隠し財産”という言葉は、実体よりも印象が先行する。
実際、裁判所が問題にするのは“隠したかどうか”ではなく、“合理的な説明ができるかどうか”だ。つまり、疑われるのは行動ではなく沈黙である。」
「たとえば、婚姻期間中に形成された預貯金が突然消えていた場合、
それが生活費として使われたのか、第三者に贈与されたのか、あるいは単に別口座に移されたのか——
その説明責任は、消失を主張する側にある。」
「判例(大阪高裁令和3年)では、妻が“貯蓄はない”と主張したが、
夫側は“収入からして2〜3割は貯蓄できたはず”と反論。
裁判所は“合理的支出”と認定し、隠し財産の存在は否定した。
つまり、証拠がなくても“生活の文脈”が合理性を証明することがある。」
「私はこう考える。
隠し財産とは、証拠の不在が生む疑念であり、
その疑念を晴らすのは“記録”ではなく、“物語”である。
家計簿も領収書も、単なる数字ではない。
それは、生活の軌跡であり、信頼の履歴なのだ。」
もふん補佐官の見解:「“隠した”んじゃなくて、“守った”んです」
「“隠し財産”って言葉、なんだか冷たいですよね。
まるで誰かが悪意を持って、こっそりお金をため込んでたみたいに聞こえる。
でも、実際はそんな単純じゃないと思うんです。」
「たとえば、子どもの教育費、親の介護、急な医療費。
そういう“見えない支出”って、領収書も残らないし、誰にも説明できないことが多い。
でも、それって“隠した”んじゃなくて、“守った”んですよ。家族を、生活を、自分の心を。」
「判例では“合理的な支出”って言葉がよく出てきますけど、
合理って誰の目線で決まるんでしょう?
裁判所?配偶者?それとも、その時の自分の必死さ?」
「私はこう思います。
お金の流れを説明できないことがあっても、
その時の“気持ち”や“状況”をちゃんと聞いてもらえる社会であってほしい。
記録がなくても、語れる物語がある。
それを“隠した”って決めつけるのは、ちょっと寂しいです。」
「だから私は、“隠し財産”って言葉の代わりに、
“未記録の生活費”って呼びたい。
それは、誰かを責めるためじゃなくて、
誰かの努力を見逃さないための言葉です。」
👇こちらもどうぞ

👇こちらもおすすめ
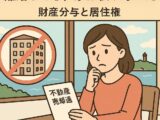
👇ご支援よろしくお願いします。
OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。
このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。
気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!
この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!
X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw
.jpg)
-1-150x150.jpg)
-150x150.jpg)






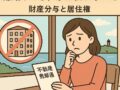
コメント