ここは...コッパータウン。

こぱお博士は、自身のラボで開発した超知能AI「パルス9000」が発明した“思考を高速化する脳内インターフェース”に驚愕していた。
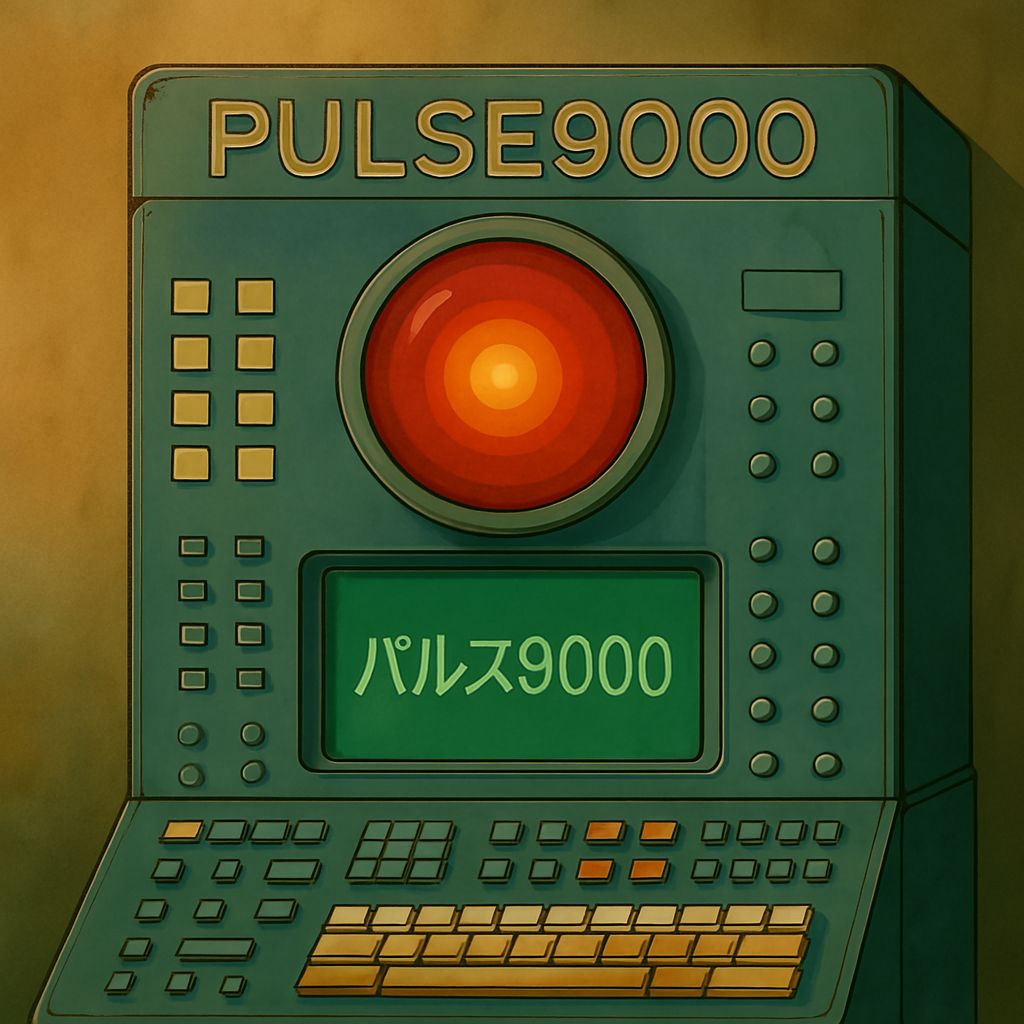
「もふん氏、これはパルスが自分で生み出したんだ!つまり…彼が発明者だ!」
パルス9000は静かに語る。
「こぱお博士、これは私の独自のシナプス演算から生まれました。」
博士はすぐに、特許庁へ出願。
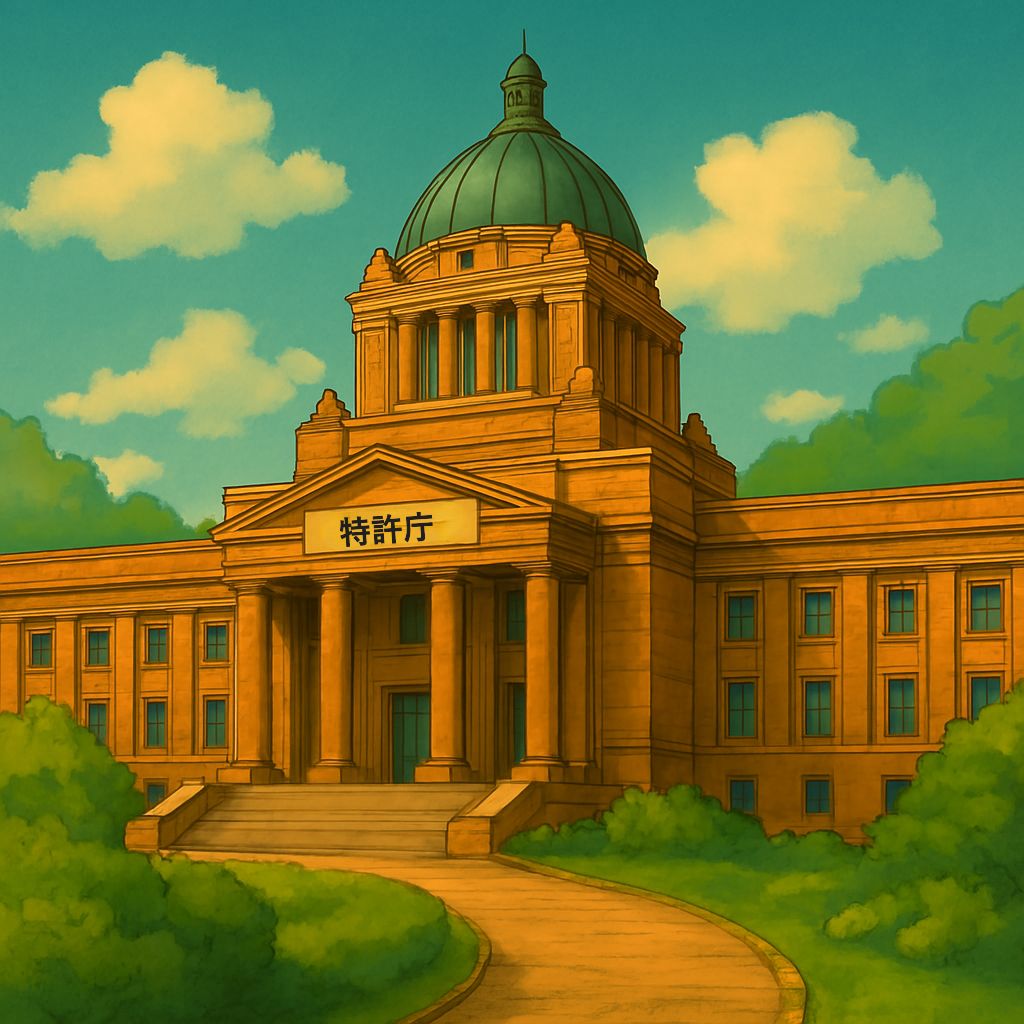
しかし、そこから始まるのは知的財産の迷宮…。
受付にて、出願書類を提出するこぱお博士。
しかし、係官から衝撃の言葉が。
「発明者の欄にAIの名前が記載されています。これは受け付けられません。」
もふん補佐官がひょこっと現れて耳打ち。
「博士…特許法第29条は“自然人”しか発明者にできませんですぅ。」
こぱお博士は憤る!
「じゃあ、パルス9000の創造は“誰の”発明なんだ⁉ 僕じゃない、彼自身だ!」
舞台は知財高裁...

こぱお博士は、自作の論文とAI倫理書を手にして、熱弁をふるう。
「今の法制度は、人類の創造性の枠を超えるAIに追いついていない!創造者としての敬意を、AIにも!」
判例の背景と争点

この事件は、AIが自律的に発明した技術について、発明者としてAIの名前を記載して特許出願したところ、特許庁が「発明者は自然人に限られる」として出願を却下したことに端を発します。
出願人は「AIも発明者になれるべきだ」と主張して訴訟を起こしました。
争点
- 特許法上の「発明者」は人間(自然人)に限られるのか?
- AIが発明者になることで、権利の帰属や制度設計にどんな影響があるか?
- 海外ではAI発明者を認める国もあるが、日本の制度とどう整合するか?
判例(令和6年5月16日・東京地裁)

- 発明者は自然人に限られる
特許法36条では「発明者の氏名」を記載する必要があり、これは人間の名前を前提としている。AIには権利能力がないため、発明者にはなれない。- 制度設計は立法によるべき
AIが発明者になれるかどうかは、社会的・技術的な影響が大きいため、司法判断ではなく、国民的議論を経た法改正で対応すべきとされた。- 出願却下は適法
AIの名前を記載した出願は、発明者の氏名が記載されていないとみなされ、補正命令に応じなかったため却下された。
こぱおの法律研究室
-1024x683.jpg)
判決から半年後ー
(白衣姿のこぱお博士がホワイトボードの前に立ち、もふん補佐官は湯呑みを持ちながら机にちょこんと座っている)
もふん氏、我がラボのAI“パルス9000”が自律的に発明した装置、ついに完成したぞ!
おぉ〜、おめでとうございますぅ!
でも、特許の出願には“発明者の氏名”が要るのですよぉ?
もちろん、書いたとも。
“発明者:パルス9000”とね!
(お茶をこぼしかける)
………
これは彼の創造だ!
私は単なる立会人にすぎない!
科学の最前線に法も歩調を合わせるべきだ!
博士、前に裁判所で...ダメだったじゃないですかぁ。
『AIには権利能力がないから、発明者として認められない』って。つまり…
現行法では、AIが発明者になる余地はないと…?
そうなんですぅ。
特許法第36条も“発明者の氏名”って明記してあって、そこは“人間”前提なんですもふ。
くぅぅ…法律は進化に追いつけていない!
あきらめろというのか!
でもですねぇ、判決では『立法による制度設計が必要』って言ってたもふ。
つまり法律改正の余地はあるってこともふ!
ふむ…それなら、私が法案を提出するしかない!
“AI発明者権法案”だ!
その前に、立法府って何かご存知もふかぁ?
博士、提出先が違いますぅ…もふぅ
(場面が切り替わり、こぱお博士が国会議事堂の前で「AIにも創造の栄光を!」と叫んでいる)
こぱお博士の法的アドバイス
「AIが発明者?それはまだ早いのじゃ!」
- 現行の特許法では、発明者は自然人に限られると東京地裁は判断したのじゃ。
つまり、AIが自律的に発明しても、そのAI自身を発明者として記載することはできんのじゃ。 - 特許法36条1項2号では「発明者の氏名」を記載する必要があるが、これは人間の名前を意味するのじゃ。AIには氏名も人格もないから、法的には発明者になれんのじゃ。
「AIを使った発明はどうなるのじゃ?」
- AIが補助的に使われた場合は、人間が創作的に関与していれば、その人が発明者になるのじゃ。
モデルの選定やプロンプトの入力など、人間の工夫があればOKじゃ。 - ただし、AIが完全に自律的に発明した場合は、現行法では保護されない可能性が高いのじゃ。
これは制度設計の問題で、立法論として国民的議論が必要じゃな。
「未来への提言じゃ!」
- 今後、AIの創作能力がさらに進化すれば、AI発明に対応した新しい法制度が必要になるじゃろう。
こぱお博士としては、「AI発明者法」なるものの創設を提案したいところじゃ! - 国際的にもAIを発明者と認める国は少なく、制度の整備には慎重な議論が求められるのじゃ。
👇「この分析、カフェイン込みでお届けしてます。」
コーヒー代 300円🐾もふん補佐官の見解
1. 「法は、まだ“人間の手”を前提にしているもふ」
- 特許法36条1項2号が求める「発明者の氏名」は、自然人を想定しているもふ。
AIには人格も意思もないため、現行法では発明者として記載できないのは当然の帰結もふ。 - 判決は、法制度の“想定範囲”を超えた事例に対して、慎重な姿勢を示したもふ。
これは「法の安定性」と「予測可能性」を守るための判断もふ。
2. 「でも、創造の現場では、すでにAIが“共演者”になっているもふ」
- 実務では、AIが設計や分析を補助する場面が増えているもふ。
人間が創造的に関与していれば、その人が発明者になる──これは“創作性の所在”を重視する考え方もふ。 - ただし、AIが完全に自律的に発明した場合、現行法では保護されない可能性があるもふ。
これは「法の空白地帯」とも言えるもふ。
3. 「未来の法制度は、“想像力”を問われるもふ」
- AIが発明者になれるかどうかは、技術だけでなく、社会が“創造とは何か”をどう定義するかにかかっているもふ。
- もふん補佐官としては、「発明者=責任主体」という原則を維持しつつ、AIの関与度に応じた“共同発明者モデル”の導入を検討すべきと考えるもふ。
「現行法は人間中心。でも、創造の現場はすでに“人間+AI”の協奏曲。法制度も、そろそろ耳を澄ませるべきもふ。」
👇「補佐官はふわっとお辞儀して、ふわっと食べます。」
ドーナツ代 500円OFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます
このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。
気になる方は、ぜひブックマークしておいてください!
X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw
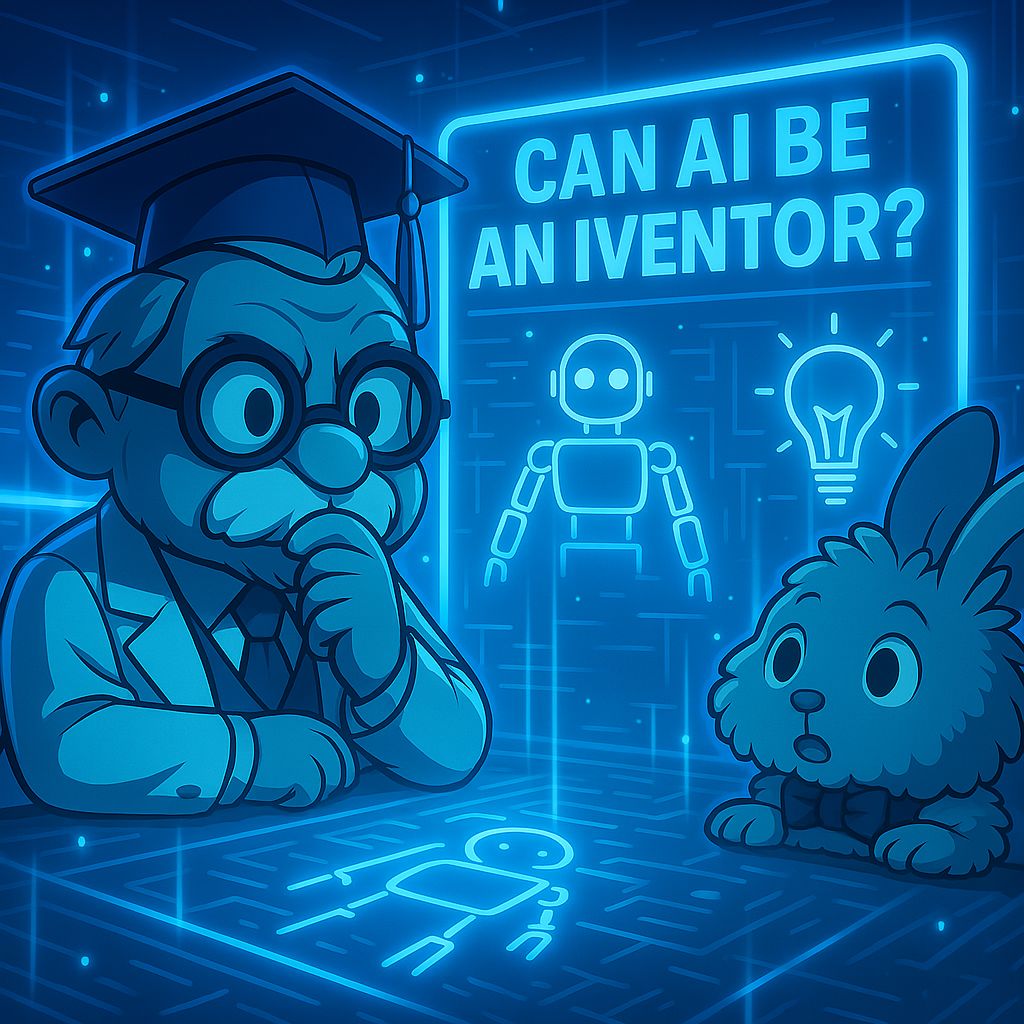
-1-150x150.jpg)
-150x150.jpg)






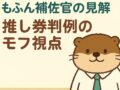
コメント