名古屋・中村区、築50年の古民家にて
障子の隙間から差し込む西日が、畳の縁を金色に染めていた。
仏壇の前に座るふみは、父の遺影に手を合わせたあと、静かに立ち上がる。
居間のちゃぶ台には、古びた封筒が三つ並んでいる。

「お兄ちゃん、これ…見てくれる?」
兄・たけしは、縁側で煙草をくゆらせていた。
灰皿代わりの空き缶には、すでに三本分の吸殻が沈んでいる。
ふみの声に振り向くことなく、ただ「うん」とだけ返す。

ふみは封筒のひとつを開け、中から黄ばんだ紙を取り出した。
筆ペンで書かれた父の字。
「借用証書」と大きく書かれ、その下に「平成15年5月10日 金五十万円也」とある。
「これ、父さんが書いたやつ。平成17年と20年にも、同じようなのがある。全部で953万円」
たけしは煙草を揉み消し、ようやくふみの方を向いた。

「そんなに…あったんだな」
「うん。でも、父さん、生前に『たけしは少しずつ返してくれてた』って言ってたよ。78万くらいは返したって」
「そうだな。何度か渡した。現金で。父さん、何も言わなかったけど…受け取ってくれてた」
ふみは、三枚の借用書を並べて見せる。

「でも、どの借金に充てたか、書いてない。たけしは、どれに返したつもりだったの?」
たけしは黙った。
ふみは言葉を選びながら続ける。
「…もし、充当指定してなかったなら、法律上は“全部の借金を認めた”ってことになるかもしれない。時効、止まってる可能性あるよ」
「時効…?」
「うん。民法145条。“債務の承認”っていうやつ。債務者が借金の存在を認めると、時効が中断されるの」
たけしは、ふみの顔をじっと見つめた。
そこには怒りも責めもなかった。ただ、父の死後に残された“整理すべきもの”を前にした、妹としての覚悟があった。

「父さん、あのとき…何も言わなかった。『ありがとう』ってだけだった」
「それが、承認だったのかもしれないね」
沈黙が流れる。
縁側の外では、夕暮れの風に揺れる柿の葉が、カサカサと音を立てていた。

👇債務整理はこちら(メール相談無料)
判例解説:最高裁令和2年12月15日判決(令和2年(受)887号)

争点
債務者が複数の借金を抱えている状態で、どの借金に充てるかを指定せずに一部返済した場合、その返済は「どの借金の時効を中断するか?」という点が争われました。
事案の概要
- 債権者(父)が債務者(長男)に対して、3回に分けて合計約953万円を貸し付けていた
- 債務者は約78万円を返済したが、どの借金に充てるかは指定していなかった
- 債権者が死亡し、相続人(妹)が残債を請求
- 債務者は「時効が成立している」と主張して争う
⚖️ 最高裁の判断

最高裁は、以下のように判断しました👇
「債務者が複数の債務の存在を認識しつつ返済した場合、充当指定がなくても、全ての債務に対して承認があったとみなされ、時効中断の効力が生じる」
つまり、債務者が「どの借金に充てるか」を明示しなかったとしても、複数の借金の存在を認識していたならば、その返済はすべての借金に対する“承認”とみなされ、時効は中断されるということです。
法的ポイント
- 民法145条:「債務の承認があったときは、時効は中断する」
- 民法488条:「充当指定がない場合、債務者の意思を推認する」
- 最高裁は「債務者が全債務を認識していた」ことを重視し、充当指定がなくても“包括的な承認”と判断
実務的な含意
- 家族間の借金でも、返済時に充当指定をしないと、全債務に時効中断が及ぶ可能性がある
- 返済の際は、領収書やメモなどで「どの借金に充てたか」を記録しておくことが重要
- 相続人が債権を請求する場合、過去の返済履歴が時効中断の根拠になる可能性がある
👇債務整理の他の記事はこちら
住宅ローン特則とは?個人再生で自宅を残すための法的ポイント | 行列のできるなんでも法律研究所
法律研究所・地下二階 雑談室
(時刻:21:48 BGM:換気扇の低い唸りと、電子レンジの「チン」)
-1024x683.jpg)
(カップ麺をすすりながら)
ふぉっふぉっふぉ…もふん氏よ、さっきの判例、なかなか味わい深いのじゃ。
借金の返済に“充当指定”がないと、全部の債務に時効中断が効くとは…まるで、味噌汁に全部の具材をぶち込んだような判定じゃのう
(メモ帳に条文を書きながら)
博士、それはちょっと乱暴な例えです…。
でも、確かに“どれに充てたか言ってない=全部認めた”っていうのは、家族間だと感情的に納得しづらいですよね
うむ。
たけし殿は78万返したが、どの借金に充てたかは言っておらん。
しかし、父上は“ありがとう”と言った…その一言が、法的には“承認”とみなされる可能性があるのじゃ
民法145条ですね。
“債務の承認があったときは、時効は中断する”。
でも、博士…承認って、言葉だけじゃなくて行動でも成立するんですよ
(目を細めて)
ふぉっふぉ…つまり、返済という行動そのものが“承認”と見なされる、と。
法は言葉よりも“動き”を見ておるのじゃな。
まるで、将棋の一手のように…
そうです。
しかも、充当指定がない場合は、民法488条で“債務者の意思を推認”するんです。
だから、複数の借金を認識していたなら、全部に効力が及ぶと判断される
ふむふむ…つまり、家族間で“言わずに返す”という美徳が、法廷では“全部認めた”というリスクになるのじゃな。
これはなかなか…切ないのう
だからこそ、返済時には“どの借金に充てるか”を明示することが大事なんです。
メモでも、領収書でも、何かしらの記録を残すべきですね
(カップ麺の残り汁をすすりながら)
ふぉっふぉ…もふんよ、わしは今、味噌ラーメンの残り汁を“平成17年の借金に充てる”と明示しておるぞ。
これで時効中断は避けられるのじゃ
(苦笑しながら)
博士、それは胃腸の時効が中断されるだけです…
👇法律を学びたい方はこちら(会員登録無料)
もふん補佐官の補足講座
テーマ:充当指定なしの返済は、なぜ時効を中断するのか?
そもそも「時効中断」って何?

債権には「時効」があります。
一定期間が過ぎると、債権者は請求できなくなる――これが「消滅時効」。
でも、ある行動をきっかけに「時効のカウントがリセット」されることがある。
それが「時効の中断」です。
代表的な中断理由👇
・債務者が借金を認める(=承認)
・債権者が裁判を起こす
・強制執行などの手続きが行われる
民法145条:「債務の承認」による時効中断
債務の承認があったときは、時効は中断する。
つまり、借金の存在を認めるような言動があれば、時効はゼロから再スタート。
ここで重要なのが、「承認」は必ずしも“言葉”でなくてもよいという点です。
返済=承認になる?
はい、なることがあります。
特に、債務者が借金を返済した場合、それは「借金の存在を認めた」とみなされる可能性が高いです。
今回の判例のポイント
・債務者は複数の借金を抱えていた
・一部返済したが、どの借金に充てたかは指定していない
・最高裁は「債務者は全ての借金の存在を認識していた」と判断
・よって、返済は“包括的な承認”とみなされ、全ての債務に時効中断の効力が及ぶ
民法488条:充当指定がない場合のルール
債務者が充当指定をしない場合、債権者の意思によって充当される。
それでも決まらない場合は、法定の順序(利息→元本→古い債務)で充当される。
つまり、指定しないと「勝手に振り分けられる」可能性があるんです。
実務で気をつけること
- 家族間でも、返済時には「どの借金に充てるか」を明示する
- メモ・領収書・メールなど、記録を残す
- 相続人が債権を請求する場合、過去の返済履歴が時効中断の根拠になることも
🐾 もふん補佐官のひとこと
「法律は“言わなかった優しさ”を拾えません。だからこそ、“記録する誠意”が大切なんです」
👇債務整理の他の記事もどうぞ

👇ご支援よろしくお願いします。
OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。
このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。
気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!
この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!
X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw
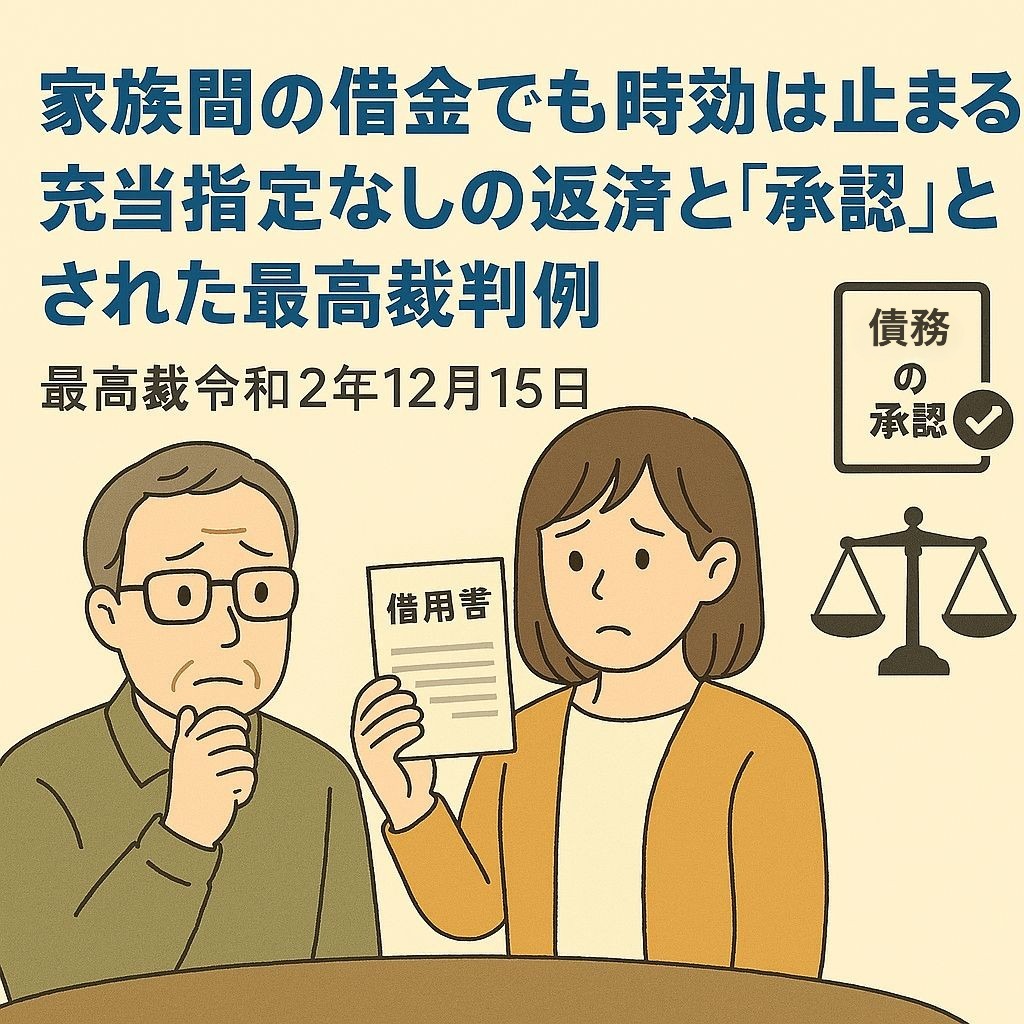
-1-150x150.jpg)
-150x150.jpg)





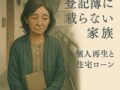

コメント