「父の遺言は、誰にも読まれなかった」
父が亡くなったのは、梅雨の終わりだった。
病室には、長男の誠一だけが呼ばれていた。
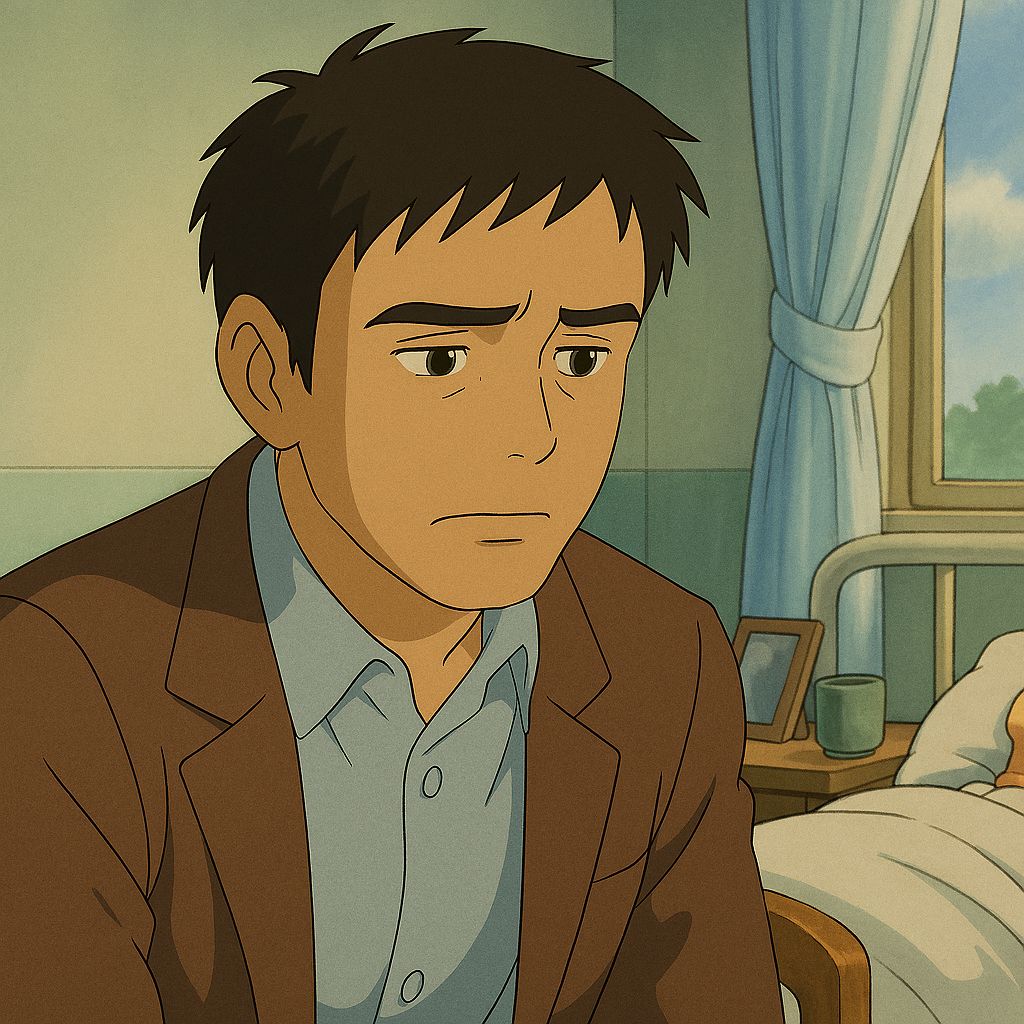
「この封筒、頼むな……」
父が差し出したのは、黄ばんだ封筒。
中には遺言書が入っていた。
誠一はそれを受け取り、黙ってポケットにしまった。
父はそれきり、言葉を発することなく息を引き取った。
葬儀のあと、親族が集まった遺産分割協議の場。
次男の健太、長女の美咲、そして父の再婚相手である綾子も席に着いた。
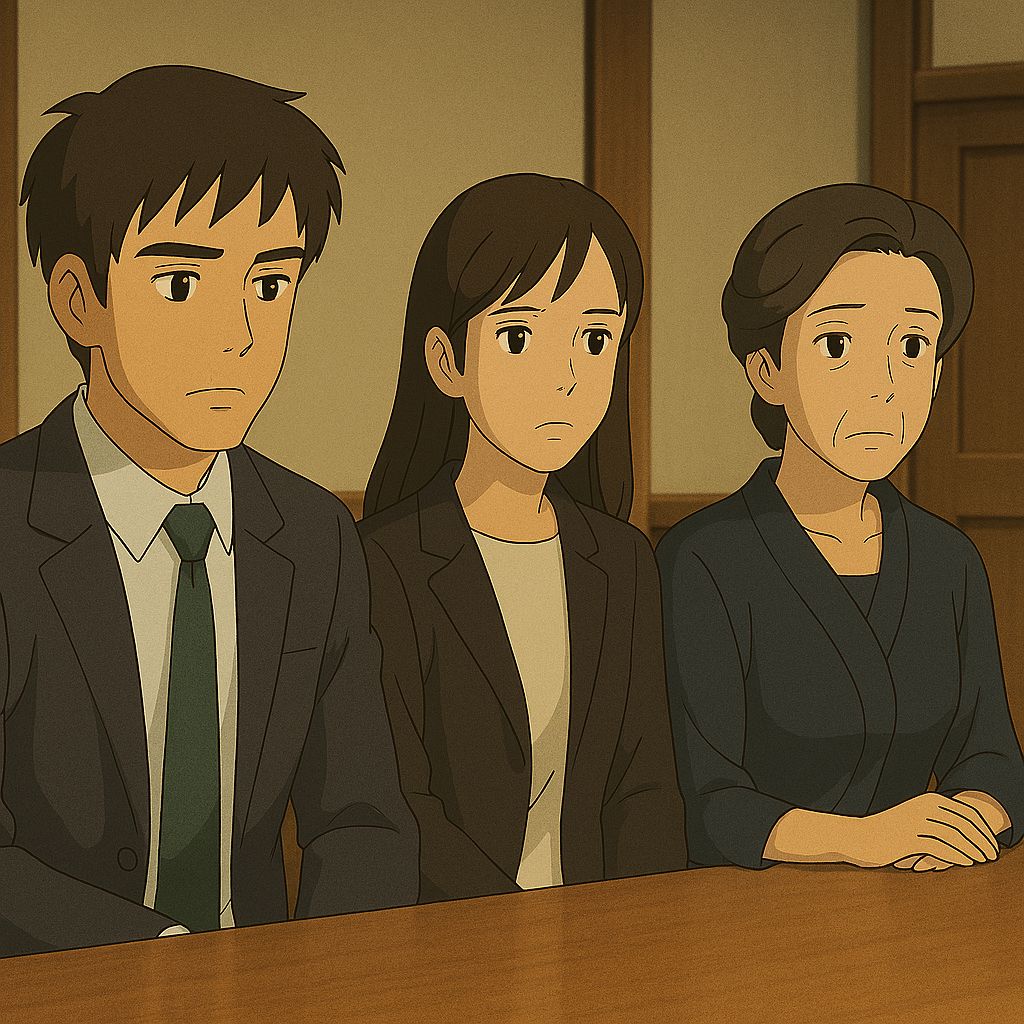
「遺言書はあるのか?」と健太が尋ねたとき、誠一は一瞬だけ目を伏せた。
「いや、父さんはそんなもの書いてないよ」
その言葉に、誰も異を唱えなかった。
協議は、誠一が主導する形で進み、土地は誠一が、預貯金は美咲と健太が分け合うことになった。
綾子には、わずかな生活費だけが渡された。
それから数ヶ月後。
健太が父の書斎を整理していたとき、引き出しの奥から一枚のコピーが出てきた。
それは、父が慈善団体への寄付を明記した遺言書の写しだった。

日付も署名もあり、封筒の色まで一致していた。
健太は誠一に問いただした。
「兄さん……これ、知ってたんじゃないの?」
誠一は黙ったまま、目をそらした。
家族の間に、静かな戦争が始まった。
「遺言書を破棄した者は、相続人として失格だ」
健太はそう主張し、家庭裁判所に申し立てを行った。
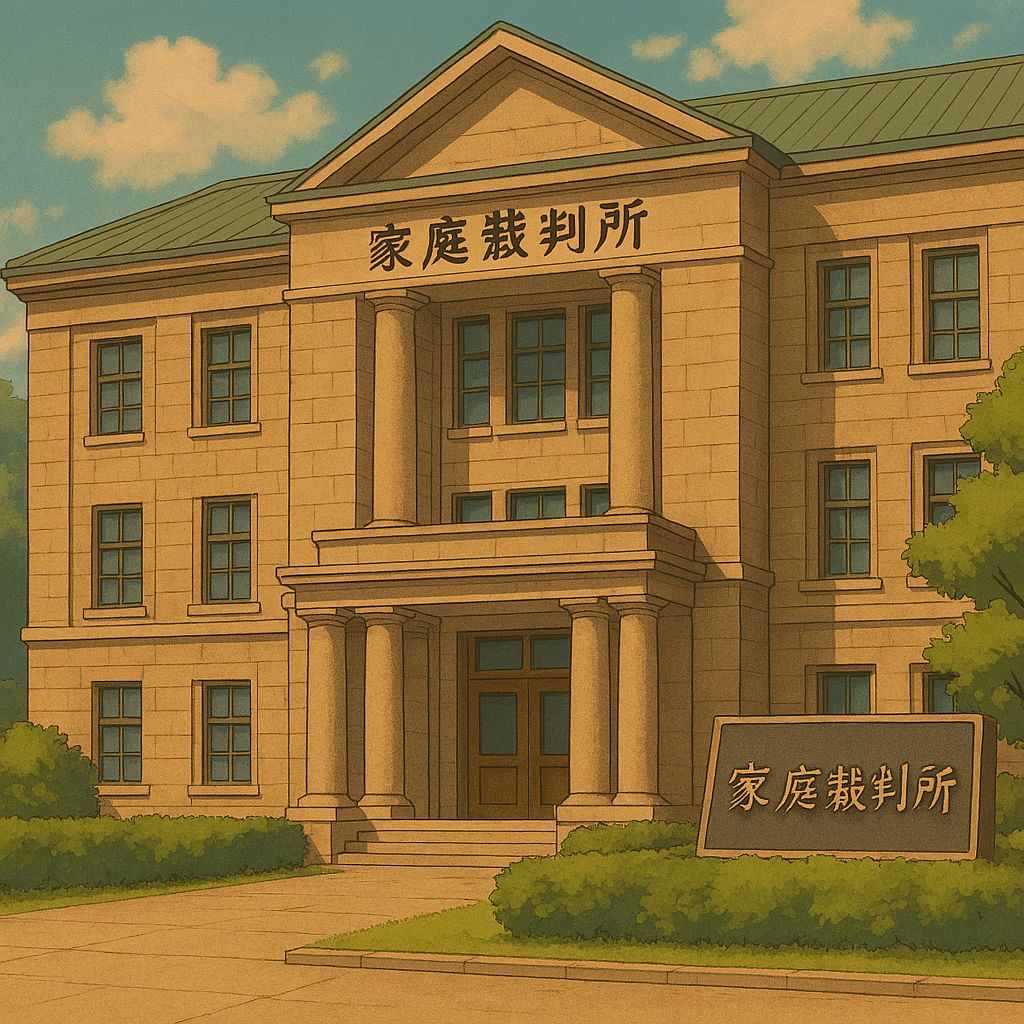
👇こちらもどうぞ
判例解説:「遺言書を破棄した相続人は欠格になるか?」

最判 平成9年1月28日(民集51巻1号184頁)
この判例では、相続人が遺言書を破棄・隠匿したとされる事案が争点となりました。
民法891条5号では、遺言書の破棄・隠匿は相続欠格事由とされています。
- 被相続人を殺害・殺害未遂
- 詐欺・脅迫による遺言の作成・取消・変更
- 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿
しかし、最高裁はこう判断しました👇
「破棄・隠匿行為が、相続に関して不当な利益を目的とするものでなければ、欠格には当たらない」
つまり、単に提示しなかっただけでは欠格にはならず、“不当な利益を得るため”という目的があったかどうかが重要なのです。
法律研究室にて
📍場面:夕暮れの法律研究室。
机の上には、黄ばんだ遺言書のコピーと民法の六法全書。
こぱお博士は眼鏡を押し上げながら、ページをめくっている。
-1024x683.jpg)
さて、もふん氏。
今日は“遺言書を破棄した相続人は欠格になるか”という判例を取り上げよう
はい。
兄が遺言書を隠してたって話、読んだけど……あれ、普通にアウトじゃないの?
民法891条5号では、確かに“破棄・隠匿”は欠格事由。
でもね、最高裁はこう言ってるんだよ
(六法を指差しながら)
“不当な利益目的でなければ、欠格には当たらない”――つまり、動機が鍵なんだ
でもさ、兄が遺言書を見せなかったことで、土地を自分のものにしたんでしょ?
それって利益目的じゃないの?
そこが難しいところ。裁判所は“故意に破棄したか”“その結果、利益を得たか”だけじゃなく、その行為に不当性があったかを見てる
じゃあ、感情的に隠しただけならセーフってこと?
理屈の上ではね。
でも、家族の信頼は別問題だ。
法は冷静でも、感情は熱い。
そこにこそ、この記事のドラマがある
うーん……法律って、冷たいようで、意外と“人の心”を見てるんだね
その通り。
だからこそ、誠実さが問われる。
遺言書を預かった者には、法的責任だけじゃなく、倫理的責任もあるんだよ
じゃあ、わたしが遺言書を預かったら……絶対に隠さないようにする!
それが一番の“家族への相続”かもしれないね
こぱお博士の見解:「法は行為を裁き、心を問う」
「遺言書を破棄した者が相続欠格に該当するか――これは民法891条5号に明記された事由だが、判例は単純な“行為の有無”だけではなく、その動機と不当性に着目している。
つまり、破棄という行為があったとしても、それが『不当な利益を得る目的』でなければ、欠格には当たらないとされる。
これは一見、法が“甘い”ように見えるかもしれないが、実は非常に繊細な判断だ。
法は冷静に事実を見つめる。
しかし、私はこう考える。
“遺言書を預かる者には、法的責任だけでなく、倫理的責任がある。
それは、亡き人の意思を守るという、静かで重い使命だ。”
仮に破棄が欠格に該当しないとしても、その行為が家族の信頼を損ない、争族を生むならば、法の外側での責任は残る。
法律は争いを裁くが、信頼は守ってくれない。
だから私は、こう結論づけたい。
“法は行為を裁く。だが、心を問うのは、私たち自身だ。”
遺言書を扱う者は、単なる相続人ではなく、故人の意思の継承者であるべきだ。
それを忘れたとき、法は許しても、家族は許さないかもしれない。
もふん補佐官の見解:「“法律でセーフ”でも、“家族ではアウト”かも」
「博士の話を聞いて、法律って思ったより“心の動き”を見てるんだなって感じた。
でも、正直に言うと――
“遺言書を隠して、自分が得するように動いた人が、欠格にならないって……なんかモヤモヤする。”
もちろん、法律にはルールがあるし、動機が不当じゃなければセーフっていうのも理屈ではわかる。
でも、家族の中でそんなことされたら、信頼は一瞬で崩れると思う。
わたしはこう思う。
“法律でセーフでも、家族ではアウトになることがある。
それって、すごく怖いことだよね。”
遺言書って、亡くなった人の“最後のメッセージ”だと思う。
それを勝手に隠したり破ったりするのは、その人の声を消すことなんじゃないかな。
だから、わたしはこう言いたい。
“遺言書を扱うときは、法律より先に、故人の気持ちを思い出してほしい。
それが、家族を守る一番のルールだと思う。”
博士みたいに法律を深く理解するのも大事だけど、わたしは“家族の空気”を守ることも、同じくらい大事だと思うんだ。」
読者の皆様への問いかけ
家族の信頼と法律の冷静さ――あなたならどうする?
遺言書を破棄した相続人が、必ずしも失格になるわけではない。
でも、家族の信頼はどうだろう?
法律が許しても、心が許さないこともある。
あなたが誠一だったら、どうしていただろう?
こぱお博士ともふん補佐官の言葉を胸に、家族の未来を考えてみてほしい。
👇こちらもどうぞ

👇ご支援よろしくお願いします。
OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。
このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。
気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!
この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!
X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw
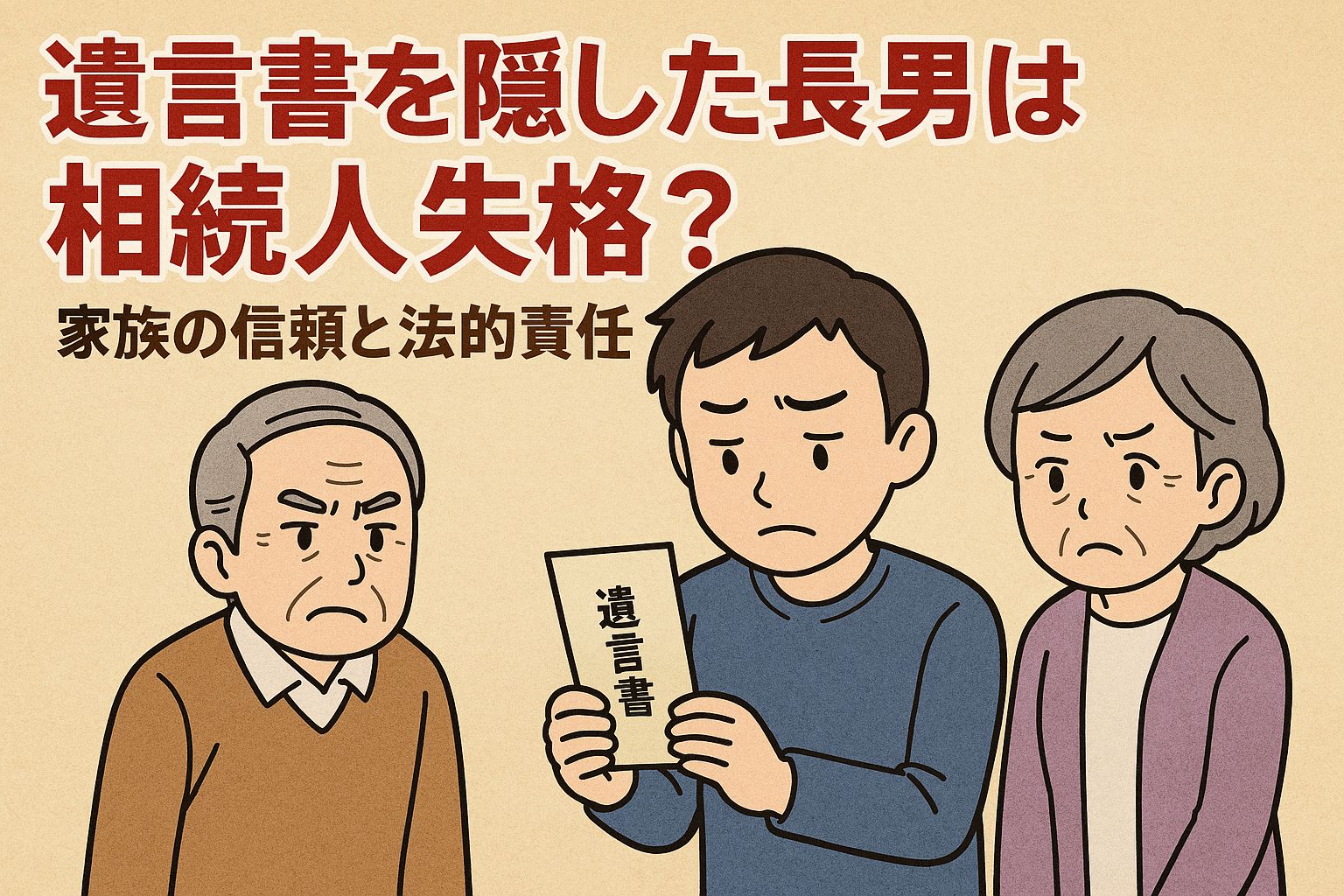
-1-150x150.jpg)
-150x150.jpg)





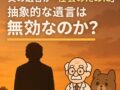
コメント