母の祈り、娘の告発──旧統一教会と不法行為の境界線
第一章:海辺の家
藤沢の海は、秋になると静かに波を打つ。
澄子(すみこ)はその音を聞きながら、朝の祈りを終えた。
居間の棚には、教会から届いた感謝状と献金証明書が並ぶ。
.jpg)
娘の遥(はるか)が家を出てから、もう十年が経つ。
「神様、あの子をお導きください…」
澄子はそう呟きながら、遥の写真に手を合わせた。
第二章:告発の書類
東京・永田町の一室。
遥は弁護士・藤堂の前に座っていた。
机の上には、旧統一教会に対する損害賠償請求訴訟の書類が並ぶ。

「本当に、やるんですね?」
藤堂の問いに、遥は頷いた。
「母は、私の進学資金を“霊感商法”で献金しました。あれは信仰じゃない。搾取です」
藤堂は静かに民法709条の条文を開いた。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は…」
「宗教法人でも、社会的相当性を逸脱すれば不法行為になります。最高裁まで争う覚悟はありますか?」
遥は、母の祈る姿を思い出しながら、ゆっくりと答えた。
「はい。私は、母を救いたいんです」
第三章:法廷の再会
東京地裁。

証人尋問の日、澄子は法廷に現れた。遥と目が合った瞬間、彼女は震えながら言った。
「遥…あなたは神を裏切るの?」

遥は答えなかった。ただ、母の目に浮かぶ涙を見つめていた。
証言台では、元信者たちが次々と証言した。
高額な壺、先祖供養、献金の強要。
藤堂は冷静に尋ねる。
「それは“信仰”でしたか?それとも“恐怖”でしたか?」
判例解説:旧統一教会と民法709条の不法行為──信教の自由の限界

背景:なぜ「不法行為」が問題になったのか?
旧統一教会(世界平和統一家庭連合)は、長年にわたり「霊感商法」や高額献金による被害が社会問題となっていました。
被害者の多くは、宗教的な不安や罪悪感を煽られ、生活に支障をきたすほどの金銭を支払っていました。
しかし、宗教活動は憲法20条で「信教の自由」として強く保護されており、国家が宗教法人に介入するには慎重な判断が求められます。
そこで争点となったのが、民法709条の「不法行為」が宗教法人に適用できるかどうかでした。
民法709条とは?
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
この条文は、個人や法人が他人に損害を与えた場合に賠償責任を負うという、民事責任の基本原則です。
宗教法人も法人格を持つ以上、原則としてこの条文の適用対象となります。
争点:宗教活動は「社会的相当性」を逸脱していたか?
最高裁が注目したのは、宗教活動の「社会的相当性」でした。
つまり、宗教的な目的であっても、その手段や結果が社会的に許容される範囲を超えていれば、不法行為として認定される可能性があるということです。
最高裁の判断(2024年)

- 宗教法人であっても、社会的相当性を逸脱した行為には民法709条が適用される。
- 教義に基づく活動であっても、信者の財産や生活を著しく侵害する場合は「違法性」が認められる。
- 被害者の自由意思が著しく制限されていた場合、信教の自由の保護範囲を超える。
判例の結論
旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に対する解散命令が、民法709条に基づく「不法行為」の成立を根拠として認められました。
憲法との関係:信教の自由 vs 被害者救済
憲法20条は信教の自由を保障していますが、それは「絶対的な自由」ではありません。
判例は、信教の自由が他者の権利を侵害する場合には、一定の制限が認められるとしています。
この判例は、宗教法人に対する国家の介入の限界を示すと同時に、被害者救済の道を開いた画期的な判断です。
物語への応用ポイント
- 藤堂弁護士の台詞:「信仰は自由です。でも、自由には責任が伴います」
- 裁判官の独白:「信教の自由を守ることと、誰かの人生を守ることは、時に矛盾する」
- 読者の皆様への問いかけ:「あなたが裁判官なら、母の信仰をどう裁きますか?」
地下二階法律研究室──こぱお博士ともふん補佐官の会話
(場面:地下二階研究室。こぱお博士ともふん補佐官が並んで座っている。机の上には判例集と献金証明書のコピー)
-1024x683.jpg)
(耳をぴくりと動かしながら)
博士、これって…信仰の自由を守るために、娘の未来を犠牲にしてもいいってことですか?
(眼鏡を押し上げながら)
法的には、信仰の自由は憲法20条で保障されている。
しかし、民法709条はこう言っている。
“社会的相当性”を逸脱すれば、それは不法行為になる
(小さく唸る)
“社会的相当性”…って誰が決めるんです?
母親にとっては、神様のための献金が“相当”だったんですよ
(静かに判例集を開きながら)
だからこそ、最高裁はこう言った。
“宗教活動の名の下に、個人の財産や生活を著しく侵害する行為は、信教の自由の保護範囲を超える”
(机に頬を乗せて)
でも博士、法律って冷たいですね。
娘さんは母親を訴えたんですよ。
それって…祈りを否定することじゃないですか?
(少しだけ微笑んで)
否定ではなく、問い直しじゃよ。
祈りが誰かを傷つけるとき、それは祈りの形を変えるべきなのだ。
法はその“問い”を形にする道具じゃ
(ぽつりと)
じゃあ…博士。
この判例は、祈りを裁いたんですか?
(目を閉じて)
いや。
祈りの“届かなかった先”を見つめたんだよ
こぱお博士の見解──祈りと法の交差点にて
「もふん氏、君は“祈り”を裁けると思うかね?」
博士はそう言って、机の上に置かれた献金証明書を指差した。
「この紙切れ一枚に、母親の信仰と娘の未来が詰まっている。法は冷たいと言われるが、実はとても人間的なんだよ。なぜなら、法は“傷ついた者の声”を聞こうとするからだ」
博士は民法709条の条文を指でなぞる。
「不法行為とは、単なる加害行為ではない。“社会的相当性”を逸脱したとき、つまり“常識”の枠を超えたときに、法はそれを違法と認定する。宗教活動であっても、だ」
もふん補佐官が小さく首を傾げる。
「でも博士、信仰って常識じゃ測れないんじゃ…?」
博士は眼鏡を押し上げて、静かに答える。
「だからこそ、最高裁は“信教の自由”と“被害者の救済”の間に橋を架けた。祈りを否定するのではなく、“祈りの届かなかった先”を見つめたのだよ」
博士は判例集の余白に書き込まれたメモを見せる。
「“信仰は内面の自由である。しかし、外に現れた行為が他者を傷つけるならば、それは法の審判に委ねられる”──これは私が学生時代に書いた言葉だ。今でもそう思っている」
博士は立ち上がり、研究室の窓の外に目を向ける。
「祈りは尊い。だが、祈りが誰かの人生を奪うとき、法はその祈りに“問い”を投げかける。それが、この判例の本質だよ」
もふん補佐官の見解──それでも、祈りは人をつなぐ
「博士の言うこと、よくわかります。法は誰かの痛みに耳を傾けるためにある──それは、きっと正しいです」
もふんは、机の上の献金証明書をそっと裏返した。
「でも私は、こうも思うんです。祈りって、誰かを傷つけることもあるけど…誰かをつなぐこともあるって」
もふんは、遥と澄子の写真を見つめながら続けた。
「娘さんが母親を訴えたのは、憎しみじゃなくて、願いだったんじゃないかな。“もう、苦しまないで”って。母親が祈っていたのも、“娘が幸せになりますように”って」
もふんは、研究室の中庭を見つめた。
「祈りが届かなかったとき、法はその隙間を埋めてくれる。でも、最後に人を救うのは、やっぱり人の声なんだと思うんです。裁判が終わったあと、娘さんが母親に言った“それでも、私はあなたを愛してる”──それが、いちばん強い祈りだったんじゃないかな」
もふんは小さく笑って、こぱお博士に言った。
「博士、法って冷たいって言われるけど、こうして話してると…ちょっとだけ、あったかいですね」
博士は眼鏡の奥で目を細め、静かに頷いた。
👇ご支援よろしくお願いします。
OFUSEで応援を送るOFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます。
このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。
気になる方は、ぜひ是非ブックマークしておいてください!
この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!
X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw
に対する解散命令請求-1.jpg)
-150x150.jpg)
-1-150x150.jpg)





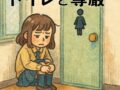

コメント