1953年、秋。
衆議院の議場は騒然としていた。

吉田首相による“抜き打ち解散”。
議員たちが呆然と席を立つなか、一人の男は静かに拳を握りしめていた。
苫米地義三。
青森三区から選ばれた、無所属の気骨ある政治家。
その目は、首相よりも、憲法を見据えていた。
苫米地は言った。
「この解散は憲法違反だ。69条にも、7条にも、該当しない」
周囲は笑った。
「議員一人が内閣に歯向かうのか?」
彼は歳費請求訴訟という一見地味な手段で、解散そのものの違憲性を問い直す。
舞台は、司法の頂点──最高裁へ。

法廷に響いた一言。
「統治行為論」。
裁判所は言った。
これは“高度に政治性のある国家行為”であり、司法は審査しない。
苫米地は法廷を出て、空を見上げた。敗れた。しかし、その問いは残った。「裁判所が審査しないなら、誰が憲法を守る?」
判決が示したのは、司法の限界と政治の暴走リスクだった。
学者は論じる。
「7条説か、69条説か?」
「解散は無制限か、制限可能か?」
彼の挑戦は判例となり、教科書に載り、未来の法律家に語り継がれていく。
事件の背景
1952年8月、吉田茂内閣は衆議院を「抜き打ち解散」。
これにより議員資格を失った苫米地義三氏が、「憲法69条に基づかない解散は違憲」として歳費請求訴訟を起こした。
争点
- 衆議院解散の効力は、裁判所が審査できるのか?
- 憲法7条 vs 69条の解釈
- 裁判所の司法権の限界とは?
👇衆議院と参議院の違いについての記事はこちら
「衆議院と参議院の違いを徹底比較|憲法・選挙制度・役割をわかりやすく解説」
最高裁の判断(最大判昭35.6.8)

- 衆議院解散は「高度に政治性のある国家行為」であり、裁判所の審査権の外にあると判断。
- 憲法7条に基づく解散は、内閣の助言と承認があれば適法とされた。
- 裁判所は違憲・合憲の判断を回避し、政治部門と国民の判断に委ねるべきとした。
判例の意義

- 統治行為論を真正面から採用した初の判例。
- 司法権の「内在的制約」論を提示し、三権分立のバランスを強調。
- 以降、裁判所は政治的判断に対して慎重な姿勢を取るようになる。
👇法律を学びたい方はこちら(会員登録無料)
こぱおの法律研究室
-1024x683.jpg)
もふん氏、最近の“衆議院解散”のニュース、どう思った?
正直に言うと、びっくり。
なんで総理がいきなり解散できるの?って思いました。
ほむ、実はそれに答えるカギが、昭和35年の判例『苫米地事件』にあるのだよ。
ここではね、“統治行為論”っていう考え方が使われたんだ。
…“とうちこういろん”?なんだか強そう……でもちょっとこわい響きですね。
簡単に言えば『政治的すぎる事案は、裁判所が口を出せない』という考え方だよ。
裁判所が“この解散は違憲かどうか”について判断を避けたのだ。
えっ、それって“誰もチェックしない”ってこと?憲法って、そういう穴あるんですか?
そこがまさに議論のポイント!苫米地義三という議員が、“違憲な解散で議席を失った”として訴えたが、最高裁は『解散は政治的すぎるから審査しない』と答えた。その姿勢が、その後の判例にも影響を与えているのだよ。
でも博士、政治的だからこそ、憲法が守られないと困るんじゃ……?もふん
いいツッコミだ!
実は統治行為論には批判も多い。
“裁判所が逃げてる”という人もいる。だが一方で、“三権分立を守るための自制”と評価する向きもある。法律って、白黒じゃなく、グレーゾーンの中に哲学があるんだ。
グレーな判例も、ちゃんと知ることが“法律を守る力”になるってことですね…!こぱお研究室、今日も深かったです!
ほむ。
次回は“69条説”と“7条説”、憲法学者たちの解散論争を紐解いていこうじゃないか。
こぱお博士の見解
🧪こぱお博士:
「苫米地事件は、ワイにとって“司法の沈黙”が最も雄弁だった判例だ。
裁判所は『政治的すぎるから審査しない』とした。つまり、憲法の番人が“門前払い”したわけだな。」
「でも、ワイはこう思うのだ。
憲法は、政治の暴走を止めるためにある。
その憲法を守るべき裁判所が、“政治的だからノータッチ”って言うたら、誰がブレーキになるのだ?」
🐾もふん補佐官(小声で):
「博士、それ、憲法学者も同じこと言ってます…」
🧪こぱお博士:
「!? でもな、苫米地さんは“歳費請求”という地味な手段で、憲法の穴を突いた。
ワイはそこに、法の美学を見たのだ。
派手な違憲訴訟じゃなく、議員としての“責任”と“誇り”をかけた静かな抵抗だ。」
「判決文には“統治行為論”という言葉は出てこない。
でもその本質は、“司法は政治に踏み込まない”という哲学だ。
それは一種の“自制”やけど、ワイはこう問いたい。
自制と逃避は、紙一重ちゃうか?」
🐾もふん補佐官:
「博士…今日、ちょっとカッコいいですね…」
🧪こぱお博士:
「ふふん。ワイはいつでもカッコいいぞぃ。
ただし、白衣にイチゴシロップがついてないとき限定だけどな!」
👇「この一杯で、憲法の解釈が3%深まるのだ。」
コーヒー代 300円もふん補佐官の見解
🐾もふん補佐官:
「苫米地事件って、最初は“むずかしい判例”って思った。でも読めば読むほど、“憲法って誰のためにあるの?”って問いが浮かんできた。」
「裁判所は『政治的すぎるから判断しない』って言ったけど、それってちょっと寂しくない?
だって、議員さんが“憲法違反かも”って訴えたのに、誰も答えてくれないなんて…。」
「でも博士が言ってたように、裁判所が全部決めちゃうと、三権分立が崩れちゃう。
だから、“司法の自制”っていう考え方も、わかる気がする。」
「もふん的には、苫米地さんの行動がすごく尊いと思う。
歳費請求っていう地味な方法で、憲法の穴を静かに突いた。
それって、“声なき声”を届けようとした勇気だと思う。」
「この事件は、“裁判所が沈黙した”っていうより、“国民が考える番だよ”って言われた気がする。
だから、もふんはこう思う。
憲法は、読まれるだけじゃなく、感じられるもの。
そして、判例はその“感じ方”を教えてくれる、ちいさな灯。」
👇「ドーナツ代で、もふんのもふもふ度が3%アップしたもふ!」
ドーナツ代 500円OFUSEでいただいた支援はキャラクターたちの”活動費”に使わせていただきます
関連記事👇
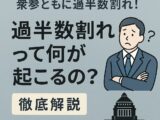
このブログでは、今後も関連テーマを深掘りしていきます。
気になる方は、ぜひぜひブックマークしておいてください!
この記事が役立ったら、SNSでシェアしていただけると幸いです!
X(旧Twitter)のフォローもお願いします。@gyoretulaw
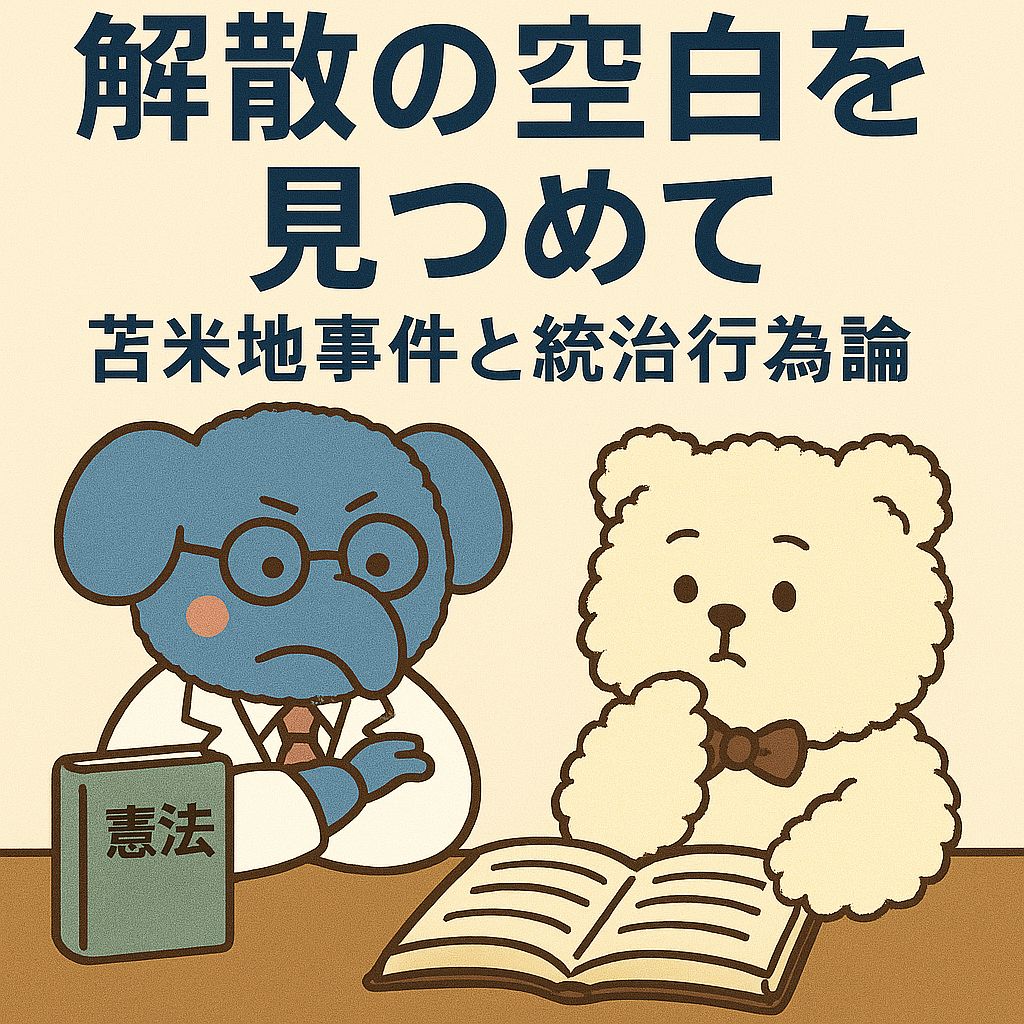
-1-150x150.jpg)
-150x150.jpg)






コメント